研究者データベース
| 林 耕史 | 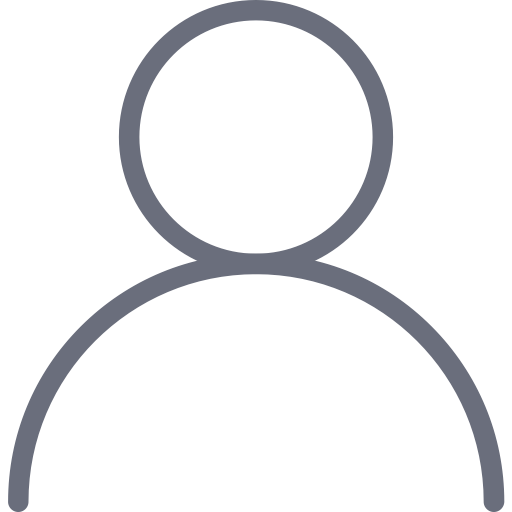 |
| ハヤシ コウシ | |
| 美術教育講座 | |
| 教授 | |
Last Updated :2025/05/29
研究者基本情報
研究者
氏名
林 耕史, ハヤシ コウシ
基本情報
研究者氏名(日本語)
林, 耕史研究者氏名(カナ)
ハヤシ, コウシ
使用外国語
発表に使用する外国語
英語執筆に使用する外国語
英語
所属
学歴
学位
所属学協会
経歴
共同研究・希望テーマ
研究活動情報
研究分野
研究キーワード
研究テーマ
- 間伐材・低質材等の木材資源を有効利用する造形用素材及び環境教育教材の開発, 木材資源 造形 彫刻 環境教育, 個人研究, 2012, 2014, 教科教育学, 科学研究費補助金
- 廃木材等を用いた「寄木技法」による彫刻の研究/ 彫刻を通した美術教育, 木彫 寄木 美術教育 , 個人研究, 2009, -, 教科教育学, その他の研究
論文
- 演奏・作曲・彫刻による「場」の創造, 菅生千穂,柏木薫,壺井一歩,林耕史, 2025年02月, 群馬大学共同教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 第60巻, 29, 44
- 立体をつくる,自分をつくる,未来をつくる, 林 耕史, 2023年01月01日, 教育美術, 第84巻, 第1号, 12, 15
- 集合体の形態で構成する彫刻による「場」の生成 Ⅱ, 林耕史, 2024年03月, 群馬大学共同教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, Annual Reports of The Faculty of Education Gunma University Art,Technology,Health and Physical Education and Science of Human Living Series, 59, 19, 27, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 集合体の形態で構成する彫刻による「場」の生成, 林耕史, 2021年03月, 群馬大学共同教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, Annual Reports of The Faculty of Education Gunma University Art,Technology,Health and Physical Education and Science of Human Living Series, 56, 17, 30, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 「造形的なやりとり」を通した協同的な造形活動の理論と実践-図画工作科教育における意義と可能性-, 林耕史, 2009年03月, 日本美術教育研究論集, 第42集, 135頁~142頁
- 「造形的なやりとり」と共生共創の造形授業, 林耕史, 2005年05月, 日本美術教育研究論集, 第38号, 101~108頁
- 「子ども力」を高める 第1年次 子ども力の基礎研究, 西村德行,濱田浩,林耕史, 2005年06月, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第61集, 83~84頁
- 「子ども力」を高める 第2年次 子ども力を高める指導法(1), 西村德行,濱田浩,林耕史, 2006年06月, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第62集, 86~89頁
- 「子ども力」を高める 第3年次 子ども力を高める指導法(2), 西村德行,濱田浩,仲嶺盛之,林耕史, 2007年06月, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第63集, 97~99,100~101頁
- 「子ども力」を高める 第4年次 子ども力を高めるカリキュラム, 西村德行,仲嶺盛之,林耕史, 2008年06月, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第64集, 119~120頁
- 「自分が情報になる」「自分がメディアになる」という感覚, 林耕史, 2006年06月, 形-Forme, 第281号, 2~5頁
- 図画工作・美術で子どもたちの側から始まる教育再生を, 林耕史, 2007年01月, 形-Forme, 第283号, 8~9頁
- 格差と競争,その量的な評価軸からの転換, 林耕史, 2007年05月, 教育研究, 第62巻, 第5号, 30~33頁
- 図画工作科の教科書のあり方とは, 林耕史, 2007年07月, 教育研究, 第62巻, 第7号, 34~35頁
- 図画工作科で「読解力」が育つ~マテリアルの「テキスト」としての位置づけ~, 林耕史, 2008年06月, 教育研究, 第63巻, 第6号, 34~35頁
- 「プロセス」は見ることができるのか, 林耕史, 2009年09月, 美育文化, 第59巻, 第5号, 13~19頁
- 廃木材等を用いた「寄木技法」による彫刻の研究, 林耕史, 2011年03月, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 第46巻, 75~88頁
- 「寄木技法」による彫刻の制作と題材化の試み, 林耕史, 2011年03月, 大学美術教育学会誌, 第43号, 295~302頁
- 彫刻を通した美術教育の在り方に関する一考察, 林耕史, 2011年03月, 日本美術教育研究論集, 第44号, 51~58頁
- OSとしての美術教育或いは美術教師, 林耕史, 2011年05月, 美育文化, 第61巻, 第3号, 48~53頁
- 「対話」をめぐる二律背反を超えて ?「変化」を楽しめる子どもたちへ?, 林 耕史, 2017年12月, 教育研究, 72, 12, 18-28
- サイト・スペシフィックとしての野外彫刻制作の試み -中之条ビエンナーレ2011『漂泊-六合の空へ』制作を通して-, 林 耕史, 2013年, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 48, 67-79
- 原木縦挽製材による板状・柱状材を用いた彫刻制作 : 「漂泊」・『月が眠る山』の制作を通して, 林 耕史, 2015年, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 50, 57-70
- 木材の端材等を有効利用する造形用素材の開発, 林 耕史, 2016年, 日本美術教育研究論集, 49, 215-222
- 教員養成課程における「彫刻」授業の在り方に関する一考察, 林 耕史, 2013年, 財団法人日本教育研究連合会記念誌, 2, 105-113
- 図画工作科の「これから」, 林 耕史, 2017年, 学校教育, 1193, 6-13.
MISC
- 「対話」をめぐる二律背反を超えて ?「変化」を楽しめる子どもたちへ?, 林 耕史, 2017年, 教育研究, 72, 12, 18, 28
- 「造形的なやりとり」と共生共創の造形授業, 林耕史, 2005年, 日本美術教育研究論集, 第38号, 101, 108
- 「子ども力」を高める 第1年次 子ども力の基礎研究, 西村德行,濱田浩,林耕史, 2005年, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第61集, 83, 84
- 「子ども力」を高める 第2年次 子ども力を高める指導法(1), 西村德行,濱田浩,林耕史, 2006年, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第62集, 86, 89
- 「子ども力」を高める 第3年次 子ども力を高める指導法(2), 西村德行,濱田浩,仲嶺盛之,林耕史, 2007年, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第63集, 97~99,100~101頁
- 「子ども力」を高める 第4年次 子ども力を高めるカリキュラム, 西村德行,仲嶺盛之,林耕史, 2008年, 筑波大学附属小学校研究紀要, 第64集, 119, 120
- 「自分が情報になる」「自分がメディアになる」という感覚, 林耕史, 2006年, 形-Forme, 第281号, 2, 5
- 図画工作・美術で子どもたちの側から始まる教育再生を, 林耕史, 2007年, 形-Forme, 第283号, 8, 9
- 格差と競争,その量的な評価軸からの転換, 林耕史, 2007年, 教育研究, 第62巻, 第5号, 30, 33
- 図画工作科の教科書のあり方とは, 林耕史, 2007年, 教育研究, 第62巻, 第7号, 34, 35
- 図画工作科で「読解力」が育つ~マテリアルの「テキスト」としての位置づけ~, 林耕史, 2008年, 教育研究, 第63巻, 第6号, 34, 35
- 「プロセス」は見ることができるのか, 林耕史, 2009年, 美育文化, 第59巻, 第5号, 13, 19
- 「造形的なやりとり」を通した協同的な造形活動の理論と実践-図画工作科教育における意義と可能性-, 林耕史, 2009年, 日本美術教育研究論集, 第42集, 135, 142
- 図画工作科の「これから」, 林 耕史, 2017年, 学校教育, 1193, 6-13.
- 廃木材等を用いた「寄木技法」による彫刻の研究, 林耕史, 2011年, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 第46巻, 75, 88
- 「寄木技法」による彫刻の制作と題材化の試み, 林耕史, 2011年, 大学美術教育学会誌, 第43号, 295, 302
- 彫刻を通した美術教育の在り方に関する一考察, 林耕史, 2011年, 日本美術教育研究論集, 第44号, 51, 58
- OSとしての美術教育或いは美術教師, 林耕史, 2011年, 美育文化, 第61巻, 第3号, 48, 53
- サイト・スペシフィックとしての野外彫刻制作の試み -中之条ビエンナーレ2011『漂泊-六合の空へ』制作を通して-, 林 耕史, 2013年, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 48, 67, 79
- 原木縦挽製材による板状・柱状材を用いた彫刻制作 : 「漂泊」・『月が眠る山』の制作を通して, 林 耕史, 2015年, 群馬大学教育学部紀要 芸術・技術・体育・生活科学編, 50, 57, 70
- 木材の端材等を有効利用する造形用素材の開発, 林 耕史, 2016年, 日本美術教育研究論集, 49, 215, 222
- 教員養成課程における「彫刻」授業の在り方に関する一考察, 林 耕史, 2013年, 財団法人日本教育研究連合会記念誌, 2, 105, 113
書籍等出版物
- 楽しさひろがる水彩指導はじめの一歩, 学事出版株式会社, 2006年, ISBN: 4761912618
- 図画工作のなぞ, 株式会社草土文化, 2007年, ISBN: 9784794509598
- 授業でそのまま使える!子どもがグーンと賢くなる 面白小話・図工編, 明治図書出版株式会社, 2008年, ISBN: 9784184306196
- 図工の授業ってどうなってるの?~「中1ギャップ」克服の第一歩~, 日本文教出版株式会社, 2009年
- 美術科教育の基礎知識, 株式会社建帛社, 2010年, ISBN: 9784767921013
- 図画工作・美術教育研究 第三版, 教育出版株式会社, 2010年
- 小学校教育課程講座 図画工作, 株式会社ぎょうせい, 2008年, ISBN: 9784324084830
- 小学校学習指導要領の解説と展開 図画工作編, 教育出版株式会社, 2008年, ISBN: 9784316802152
- 国際教育協力ハンドブック~現職派遣教員のための実践事例集~, 筑波大学附属小学校国際教育協力拠点形成プロジェクト, 2008年
- 子ども力を高める授業, 株式会社図書文化社, 2008年, ISBN: 9784810085082
- 図工の授業をデザインする, 株式会社東洋館出版社, 2008年, ISBN: 9784491023694
- 新・生活科研究 四訂版, 群馬大学教育学部生活科実施委員会, 2011年
- Art Link アート・リンク 造形・美術授業実践事例集, 日本文教出版株式会社, 2011年
- 風のなかで~むしのいのち・くさのいのち・もののいのち~(映画カタログ), 中瀬幼稚園, 2009年
講演・口頭発表等
- 大学美術教育学会シンポジウム, 林耕史,芳賀正之,村田透,冨田晃,新井浩, 第63回大学美術教育学会, 2024年09月14日, 2024年09月14日, 金沢大学
- 身体運動文化と地域シンポジウム, 林 耕史, 身体運動文化学会第29回大会, 2024年12月07日
- 立体をつくる,自分をつくる,未来をつくる, 林 耕史, 2023年08月04日, 茨城県近代美術館
- 中之条芸術大学, 林耕史, 中之条芸術大学「まなび±アート×研究」, 2021年09月18日
- 木片でつくる小さな彫刻, 林耕史, 「林耕史展」美術館ワークショップ, 2018年03月24日, 渋川市美術館・渋川市
- 今,図画工作科・美術科の授業で大切にしたいこと, 林耕史, 長野県美術教育研究大会・下伊那大会, 2020年11月13日
- 林耕史個展クロスオーバー, 林耕史, Adams State University Artist in Residency Program, 2019年09月23日, 2019年10月04日
- 美術学部彫刻講義, 林耕史, Adams State University Artist in Residency Program, 2019年10月02日
- 水墨画ワークショップ, 林耕史, Adams State university Artist in Residency program events, 2019年09月28日, 2019年09月28日
- 「造形的なやりとり」を通した協同的な造形活動の理論と実践, (社)日本美術教育連合, 2008年
- 「造形的なやりとり」と共生共創の造形授業, (社)日本美術教育連合, 2004年
- 「造形的なやりとり」と共生共創の造形授業-2-, (社)日本美術教育連合, 2005年
- 彫刻を通した美術教育の在り方に関する一考察, 公益社団法人日本美術教育連合, 2010年
Works(作品等)
- 月が眠る山2024-Ⅷ, Mountain The Moon Sleeps 2024-8, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年11月17日, 2024年12月08日, 飯田市美術博物館 長野, 第24回現代の創造展 出品彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅶ, Mountain The Moon Sleeps 2024-7, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年11月01日, 2024年11月08日, 東京都美術館, 第98回国画会秋季展出品彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅵ, Mountain The Moon Sleeps 2024-6, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年10月05日, 2024年10月20日, 桐生市有鄰館 群馬, 桐生市有鄰館ビエンナーレ2024発表彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅴ, Mountain The Moon Sleeps 2024-5, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年10月05日, 2024年10月20日, 桐生市有鄰館 群馬, 桐生市有鄰館ビエンナーレ2024 発表彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅳ, Mountain The Moon Sleeps 2024-4, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年09月23日, 2024年09月23日, 高崎シティギャラリー・コアホール 群馬, 菅生千穂クラリネット・リサイタル ステージ構成彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅲ, Mountain The Moon Sleeps 2024-3, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年07月19日, 2024年07月24日, 高崎シティギャラリー 群馬, 第18回国展群馬出品彫刻
- 月が眠る山2024-Ⅱ, Mountain The Moon Sleeps 2024-2, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2024年05月01日, 2025年05月13日, 国立新美術館
- ライヴセッション「音のスケッチ 彫刻をみる/音楽でみる」, 林 耕史 菅生千穂, Koshi HAYASHI , Chiho SUGO, 2024年02月17日, 2024年02月17日, 群馬県立館林美術館, 彫刻家と音楽家によるセッションに演奏家として出演。展示作品のイメージや印象を演奏。解説も加え,来場者と鑑賞する演奏会。
- 月が眠る山2023-Ⅶ, Mountain the Moon Sleeps 2023-7, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2023年11月01日, 2023年11月08日, 東京都美術館, 第97回国画会秋季展出品作。同年10月発表の演奏会舞台構成にて使用した同一素材であるが,美術館空間に対応して再構成した作品である。
- 月が眠る山2023-Ⅶ, Mountain the Moon Sleeps 2023-7, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2023年10月21日, 2023年10月21日, マリーコンツェルト(東京), コンサートにおける舞台構成として彫刻を制作,設置したものである。
- わたしを気にする〜わたしが木になる, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2023年09月09日, 2023年10月09日, イサマムラ伊参公民館(群馬 中之条町), 身体を木に置き換える〜自分の身体を客観的に見つめ直す機構としての多様な木片による場の構成と提示
- ざくざく, Zaku - Zaku, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2023年02月04日, 2023年05月09日, 長野県立美術館(長野市), アートラボ2022「ひらくツール」展出品
- 月の森 Ⅰ, The Moon Forest 1, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2022年11月07日, 2022年12月03日, ヤマトギャラリー(前橋市), 「ミルコト,ミエナイコト,サワルコト〜感じる彫刻展」=視覚に障がいがある人でも誰でも触れて感じ楽しめる彫刻展への出品作
- 月の森 Ⅱ, The Moon Forest 2, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2022年11月07日, 2022年12月03日, ヤマトギャラリー(前橋市), 「ミルコト,ミエナイコト,サワルコト〜感じる彫刻展」=視覚に障がいがある人でも誰でも触れて感じ楽しめる彫刻展への出品作
- 山に帰る月, The Moon Returning to Mountain, 林 耕史, Koshi HAYASHI, 2022年11月01日, 2022年11月08日, 東京都美術館, 第96回国画会秋季展
- 月が眠る山 2022-Ⅰ, Mountain the Moon Sleeps 2022-I, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2022年10月07日, 2022年10月23日, 有鄰館(桐生市), 第96回国展出品作と同一であるが,展示場所ロケーションにあわせて構成,発表した。
- 月が眠る山 2022-Ⅰ, Mountain the Moon Sleeps 2022-I, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2022年05月04日, 2022年05月16日, 国立新美術館
- 月が眠る山2020-Ⅲ, Mountain The Moon Sleeps 2020-3, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2020年11月15日, 2020年12月06日, 第21回現代の創造展 飯田市美術博物館
- 音を見る/形を聴く スモール・ライヴ・セッション, Watching the Sounds / Listening the Forms SMALL LIVE SESSION, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2021年10月24日, 2021年10月24日, 中之条ビエンナーレ2021 群馬県中之条町, 同展出品彫刻作品が設置されている野外スペースで,アコースティック楽器を用いて空間を構成する試みを一般公開した。
- 月が眠る山2023-Ⅵ, Mountain The Moon Sleeps 2023-6, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2023年09月09日, 2023年10月09日, 中之条ビエンナーレ2023 群馬県中之条町, 中之条ビエンナーレ2023に出品展示。暮坂峠の山間地のロケーションを活かした彫刻展示を試みた。
- 月が眠る山2021-Ⅱ, Mountain The Moon Sleeps 2021-2, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2021年10月, 2021年11月, 中之条ビエンナーレ2021 群馬県中之条町, 中之条ビエンナーレ2021に出品展示。暮坂峠の山間地のロケーションを活かした彫刻展示を試みた。
- 月が眠る山 2021-Ⅰ, Mountain The Moon Sleeps 2021-1, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2021年07月, 2021年07月, 国立新美術館(誌上発表),高崎シティギャラリー, 第95回国展出品(コロナ対応により不開催につき図録誌上発表)および第15回国展群馬に出品,展示発表。
- 月が眠る山2020-Ⅰ MAEBASHI, Mountain the Moon Sleeps 2020-1, 林耕史, Koshi Hayashi, 2020年, 前橋の美術2020・アーツ前橋
- 月が眠る山〜ここに生まれて, Mountain the Moon Sleeps - Born here, and..., 林耕史, 2019年, 中之条ビエンナーレ2019・中之条町
- 月が眠る山〜緑の丘に, Mountain the Moon Sleeps - On the green hill, 林耕史, Koshi Hayashi, 2019年, 中之条ビエンナーレ2019 ・ 中之条町
- 月が眠る山2019-Ⅵ NAKANOSAWA, Mountain the Moon Sleeps 2019-VI NAKANOSAWA, 林耕史, 2019年, 中之沢美術館・前橋市
- 月が眠る山2019-Ⅶ ALAMOSA, Mountain the Moon Sleeps 2019-VII ALAMOSA, 林耕史, 2019年, クロイド・スヌーク・ギャラリー ・ コロラド,アメリカ
- 月が眠る山2019-Ⅰ , Mountain the Moon Sleeps 2019-1, 林耕史, 2019年, 第93回国展・国立新美術館
- 月が眠る山2018-Ⅲ, Mountain the Moon Sleeps 2018-III, 林耕史, 2018年, 第92回国展・国立新美術館
- RIN 2018-Ⅰ, RIN 2018-I, 林耕史, Koshi Hayashi, 2018年, 『林耕史展」・渋川市美術館・渋川市
- 月が眠る山2018-Ⅱ, Mountain the Moon Sleeps 2018-II, 林耕史, 2018年, 「林耕史展」渋川市美術館・渋川市
- 月が眠る山2018-Ⅰ, Mountain the Moon Sleeps 2018-I, 林耕史, 2018年, 『林耕史展」渋川市美術館・渋川市
- 林耕史個展『漂泊 2013-Ⅰ』 出品, 2013年
- 第7回国展群馬『漂泊-ひとつの樹としてⅡ-』出品, 2013年
- 第87回国展「漂泊2013-Ⅱ」出品, 2013年
- 緑の中の小さな彫刻展vol.2『月を運ぶ舟Ⅰ』出品, 2013年
- 緑の中の小さな彫刻展vol.2『月を運ぶ舟Ⅱ』出品, 2013年
- 第8回国展群馬『漂泊2013-Ⅲ』出品, 2013年
- 林耕史展におけるレクチュア+ワークショップ, 2013年
- 林耕史展におけるライヴセッション, 2013年
- 南信州ゆかりのアーティスト展『漂泊 -時間層Ⅱb-』 発表, 2012年
- 第35回国画会彫刻部秋季展「漂泊-明日へ届けるⅢ」出品, 2012年
- 飯伊50人展『漂泊 -祈りⅡ-』発表, 2012年
- 第12回現代の創造展『漂泊 -ひとつの樹に-』 出品, 2012年
- 緑の中の小さな彫刻展『漂泊 -明日へ届けるⅠ-』出品, 2012年
- 緑の中の小さな彫刻展『漂泊 -明日へ届けるⅡ-』出品, 2012年
- 上越教育大学・信州大学・群馬大学彫刻研究室合同展覧会2012『漂泊-明日へ届けるⅡ』出品, 2012年
- 第86回国展「漂泊-ひとつの樹として-」出品, 2012年
- 第4回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~ひとつの樹に~』出品, 2011年
- 第85回国展「漂泊~祈り」出品, 2011年
- 国画会彫刻部受賞作家展「漂泊~時間層Ⅱb」出品, 2011年
- 中之条ビエンナーレ2011「漂泊~六合の空へ~」出品, 2011年
- 第34回国画会彫刻部「試み展」「漂泊~祈りⅡ」出品, 2011年
- 中之条ビエンナーレ2011アーティストトーク, 2011年
- 第10回現代の創造展『漂泊~寄港地~』出品, 2010年
- 第84回国展『漂泊~入江の音~』出品, 2010年
- 第3回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~城壁の記憶~』出品, 2010年
- 第3回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~明日の記憶~』出品, 2010年
- 第3回次代を担う彫刻家たち展『漂泊(2009)』出品, 2010年
- 第83回国展『漂泊~寄港地』出品, 2009年
- 第2回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~寄港地』出品, 2009年
- 第2回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~月の鞘』出品, 2009年
- 第33回国画会彫刻部試み展『漂泊(2009)』出品, 2009年
- 第82回国展『漂泊~明日の行方~』出品, 2008年
- 第32回国画会彫刻部試み展『漂泊(2008)』出品, 2008年
- 第8回現代の創造展『漂泊~時間層~』出品, 2008年
- 第81回国展『漂泊~時間層~』出品, 2007年
- 第31回国画会彫刻部秋季展『漂泊(2007)』出品, 2007年
- 信州のカタチ展『漂泊~時間のいれもの~』出品, 2006年
- 信州のカタチ展『漂泊(2005)』出品, 2006年
- 第1回次代を担う彫刻家たち展『漂泊(2005)』出品, 2006年
- 第6回現代の創造展『漂泊~時間のすみか~』出品, 2006年
- 第80回国展『漂泊~時間のいれもの~』出品, 2006年
- 信州のカタチ展『漂泊~時間のすみか~』出品, 2006年
- 第1回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~坂道~』出品, 2006年
- 第1回次代を担う彫刻家たち展『漂泊~失われた時間~』出品, 2006年
- 第30回国画会彫刻部秋季展『漂泊(2006)』出品, 2006年
- 第79回国展『漂泊~時間のいれもの~』出品, 2005年
- 第29回国画会彫刻部秋季展『漂泊(2005)』出品, 2005年
- 第78回国展『漂泊~記憶の向こう側へ~』出品, 2004年
- 第28回国画会彫刻部秋季展『漂泊~ふたつの旅~』出品, 2004年
- 音にふれる/形にふれる スモール・ライヴ・セッション2023, Touch the Sounds / Feel the Shape SMALL LIVE SESSION 2023, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2023年09月16日, 2023年09月16日, 中之条ビエンナーレ2023 群馬県中之条町, 同展出品彫刻作品が設置されている野外スペースで,アコースティック楽器を用いて空間を構成する試みを一般公開した。クラリネット奏者,笙演奏家とのコラボが実現。
- 月が眠る山 2023-Ⅰ, Mountain the Moon Sleeps 2023-I, 林耕史, HAYASHI Koshi, 2023年05月03日, 2023年05月15日, 国立新美術館
受賞
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 間伐材・低質材等の木材資源を有効利用する造形用素材及び環境教育教材の開発, 科学研究費補助金, 2012年, 2014年, 競争的資金
- 廃木材等を用いた「寄木技法」による彫刻の研究/ 彫刻を通した美術教育, その他の研究制度, 2009年, 競争的資金
- 間伐材・低質材等の木材資源を有効利用する造形用素材及び環境教育教材の開発, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2012年, 2014年, 競争的資金
- Study on Sculpture with A Technique of Assembling Pieces of Wood Called Yosegi-giho/Art Education through Sculpture, The Other Research Programs, 2009年, 競争的資金
社会貢献活動情報
社会貢献活動
- 令和6年度群馬大学共同教育学部附属特別支援学校公開研究会シンポジウム
- 第49回みどりの絵コンクール作品審査, 公益財団法人三菱UFJ環境財団, みどりの絵コンクール, 2024年10月11日, 2024年10月25日
- インクルーシブアートコーディネーター養成講座開設に向けたプロジェクト, 文化庁委託事業である「令和5年度 障害者等による文化芸術活動推進事業」の申請者(群馬大学)における代表者として,企画,参画ならびに研究会講師としての参加など,活動した。
- 令和5年度前橋市図工美術実技研修会, 2023年07月28日, 2023年07月28日
- インクルーシブアートコーディネーター研究会 第8回「感じる彫刻展でミエタコト」, 文化庁委託事業 インクルーシブアートコーディネーター養成講座開設に向けたプロジェクト実行委員会, 2023年12月18日, 2023年12月18日, 群馬大学(対象:大学生, 大学院生, 社会人・一般)
- 第58回新潟県中越教育美術展作品審査, 2022年12月02日, 2022年12月02日, 長岡市立上組小学校
- 第74回長野県美術教育研究大会講演会, 長野県美術教育研究会, 2020年11月13日, 2020年11月13日, 長野県下伊那郡松川町中央公民館, 美術教育研究大会テーマ「ひぎき合う感性」および参観授業内容・研究に対応した今日的な課題を講演した。(対象:教育関係者, 研究者)
- 第59回関東甲信越静地区造形教育研究大会, 2019年11月15日, 標記研究大会公開保育における指導助言を行った。(対象:教育関係者, 研究者)
- 平成31年度公開研究会シンポジウム, 群馬大学教育学部附属幼稚園, 2019年10月19日, 群馬大学教育学部附属幼稚園, 「幼児の遊びを豊かにする園舎・園庭の在り方」というテーマの下,基調提案およびシンポジウムにあたった。(対象:教育関係者, 研究者)
- 平成31年度研修講座「新任幼稚園長等研修」, 群馬県総合教育センター幼児教育センター, 2019年05月21日, 新園長等の職につく教員に円のカリキュラム・マネジメントなど経営者として在り方をレクチャした。
- 校内研修会, 前橋市立原小学校, 校内研修会, 2019年01月23日, 平成31年度関ブロ造形教育研究大会に向けて校内の図画工作科教育についての公演,実地指導を行った。
- 平成30年度伊勢崎市立幼稚園一日研修会, 伊勢崎市教育委員会, 2018年11月16日, 伊勢崎市立あかぼり幼稚園, 幼稚園教員に向けての造形活動を通した保育について講演した。(対象:教育関係者, 研究者)
- 第53回郡山市子ども総合美術展審査会, 2018年11月13日, 郡山市青少年会館, 小学生図画工作科作品の審査(対象:教育関係者)
- 平成29年度茨城県教育研究会図工・美術教育研究部夏季実技研修会, 茨城県教育研究会, 2018年08月01日, 図画工作科「立体に表す」内容についての実技講習。(対象:教育関係者)
- 第70回全国造形教育研究大会, 全国造形教育連盟・長野県美術教育研究会, 2017年
- 第5回小学校教育研究会, 小田原市小学校教育研究か, 2016年10月21日
- 平成28年度伊勢崎市教育研究所幼保小連携研修講座, 伊勢崎市教育研究所, 2016年07月22日, 伊勢崎市円形交流館「絣の郷」(対象:教育関係者)
- 夏の造形研修会, 名古屋市造形教育研究会, 2015年08月07日, 名古屋市立駒方中学校(対象:教育関係者)
- 第59回新潟県中越教育美術展作品審査, 2023年12月01日, 2023年12月01日, 長岡市立上組小学校
- 第18回新潟教育アート展作品審査, 2022年11月28日, 2022年11月28日, 新津美術館
- 第19回新潟教育アート展作品審査, 2023年11月28日, 2023年11月28日, 新津美術館
- 第48回みどりの絵コンクール作品審査, 2023年10月13日, 2023年10月27日, 公益財団法人 三菱UFJ環境財団
- 第47回みどりの絵コンクール作品審査, 2022年10月07日, 2022年10月21日, 公益財団法人 三菱UFJ環境財団
- 令和4年度前橋市図工美術実技研修会, 2022年07月29日, 2022年07月29日
