研究者データベース
| 新藤 慶 | 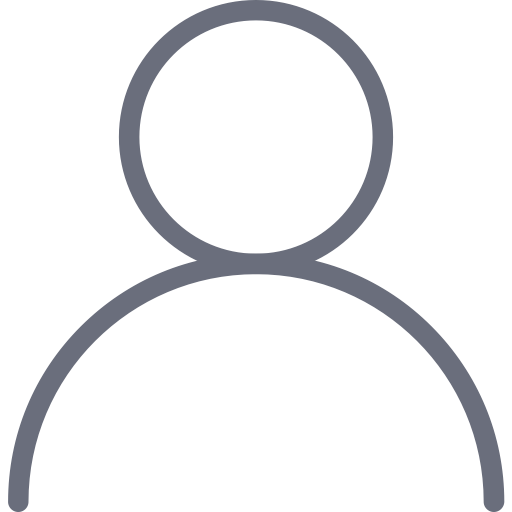 |
| シンドウ ケイ | |
| 学校教育講座 | |
| 教授 | |
Last Updated :2025/05/29
研究者基本情報
研究者
氏名
新藤 慶, シンドウ ケイ
基本情報
研究者氏名(日本語)
新藤, 慶研究者氏名(カナ)
シンドウ, ケイ
使用外国語
発表に使用する外国語
英語執筆に使用する外国語
英語
所属
学歴
学位
所属学協会
経歴
研究活動情報
研究分野
研究キーワード
研究テーマ
- 住民運動における地域住民の学習過程, 住民運動、地域社会、学習過程, 個人研究, 教育社会学, その他の研究
- 市町村合併に伴う地域社会の共同性の変容, 市町村合併、地域社会、共同性, 個人研究, 社会学, 科学研究費補助金
- 在日ブラジル人の教育と保育, 在日ブラジル人、教育、保育, 国内共同研究, 教育社会学, 科学研究費補助金
論文
- 教育社会学における「地域」の位置 : 社会化,選抜・配分,政策,学校をめぐる研究動向から, 尾川満宏・上山浩次郎・新藤慶・知念渉, 2024年12月, 教育社会学研究, 115, 51, 108
- 外国籍住民の集住地域の中学校教員からみた外国籍生徒の学習と進路の現状と課題 ―教員への聞き取り調査の記録―, 新藤慶・高島裕美, 2025年03月, 群馬大学教育実践研究, 42, 117, 143, 研究論文(学術雑誌)
- 外国につながる子どもの困難と地域社会の新たな関係 : 子どもの日本語能力と進路保障をめぐる地域社会の現状を通して, 新藤慶, 2024年05月, 地域社会学会年報, 36, 26, 41, 研究論文(学術雑誌)
- インターセクショナリティ研究の動向と課題, 上山浩次郎・野崎剛毅・濱田国佑・新藤慶, 2024年06月, 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 144, 199, 222, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 高等学校に在籍する外国人生徒の実態に関する基礎資料: 政府統計を組み合わせた分析をもとに, 新藤慶, 2024年03月, 群馬大学教育実践研究, 41, 187, 198
- 在留外国人の階層再生産構造と教育の課題: エスニシティの違いに着目して, 新藤慶, 2023年03月01日, 群馬大学教育実践研究, 40, 211, 220
- 在留外国人の子どもの教育からみた多文化共生社会: 群馬県大泉町におけるブラジル人の事例を中心に, 新藤慶, 2022年06月, 現代社会学研究, 35, 39, 60, 研究論文(学術雑誌)
- 外国につながる子どもの日本語指導の必要性と教育達成の関連 : 文部科学省「日本語指導が必要な児童 生徒の受入状況等に関する調査」の検討を中心に, 新藤慶, 2022年02月, 群馬大学共同教育学部紀要 人文・社会科学編, 71, 121, 135
- 多文化共生社会の構築と学校の機能 : 在日ブラジル人とアイヌ民族の状況を中心に, 新藤慶, 2021年06月, 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 138, 77, 96
- 主体的に学ぶ生徒を育成する学校づくり: 「柔軟なスタンダード」を活用した授業改善と家庭学習改善の組織的取組を通して, 長井敦則・新藤慶・野村晃男, 2022年03月, 群馬大学教育実践研究, 39, 245, 254
- 日本語指導の必要性と外国人の子どもの在留資格: 法務省「在留外国人統計」からみる外国人の子ども, 新藤慶, 2022年03月, 群馬大学教育実践研究, 39, 159, 169
- 外国人の子どもを対象とした貧困研究の成果と教育実践上の課題, 新藤 慶, 2021年03月, 群馬大学教育実践研究, 38, 287, 296
- 外国につながる子どもの教育支援に対する教師の関心と在日外国人と教育に関する教育社会学的研究の知見, 新藤慶・清水喜義, 2019年03月15日, 群馬大学教育実践研究, Research in Educational Practice and Development, Gunma University, 36, 0, 153, 163
- アイヌ文化学習の論理と展望――北海道白糠町の事例を通して, 新藤 慶, 2018年, 群馬大学教育実践研究, 35, 193, 204
- 布施鉄治の地域研究における調査と方法――村研での発表論文・夕張調査を中心として, 新藤 慶, 2017年, 村落社会研究ジャーナル, 23, 2, 25, 35
- 小学校教員の資質能力に関する教員自身の自己評価や認識, 矢島 正,髙橋 望,新藤 慶, 2017年, 群馬大学教育実践研究, 34, 127, 140
- 実習校生徒評価を通じた教職大学院教育の成果と課題 ― 現職院生の工業高校での実習・研究を事例として ―, 新藤 慶,矢島 正,髙橋 望,柴山 和宏, 2016年, 群馬大学教育実践研究, 33, 123, 131
- 群馬県版校務支援標準システムの導入とその効果分析, 矢島 正,髙橋 望,新藤 慶,三好 賢治,二宮 一浩, 2016年, 群馬大学教育実践研究, 33, 199, 208
- 群馬大学教職大学院の修了生への調査からみられる教職大学院の成果と改善点の検討Ⅲ ― ストレートマスターへの個別インタビュー調査分析 ―, 山口 陽弘,新藤 慶, 2015年, 群馬大学教育実践研究, 32, 217, 226
- 初任者教員に期待される職務能力基準(試案) ― 小学校2年生・4年生の「学習指導」「学級経営」「生徒指導」を例に ―, 矢島 正,髙橋 望,新藤 慶,山本 宏樹, 2015年, 群馬大学教育実践研究, 32, 203, 215
- 産炭地における子どもの姿と教育実践――1950年代~1960年代前半の研究をもとにして, 新藤 慶, 2015年, 群馬大学教育実践研究, 32, 123, 134
- 群馬大学教職大学院の修了生への調査から見られる教職大学院の成果と改善点の検討Ⅱ ― 個別インタビュー調査に焦点化して ―, 山口 陽弘,新藤 慶, 2014年, 群馬大学教育実践研究, 31, 173, 183
- 教員の職務負担と解決方法 ― 群馬県での公立学校教員調査を通して ―, 新藤 慶,矢島 正,髙橋 望,青木 美恵,柵木 みどり, 2014年, 群馬大学教育実践研究, 31, 137, 152
- 群馬大学教職大学院の修了生調査からみられる教職大学院の成果と改善点の検討, 新藤 慶,山口 陽弘, 2013年, 群馬大学教育実践研究, 30, 145, 155
- 大学教職員のキャンパス・ハラスメント予防への意識――2010年度人権啓発研修会前後の意識変化と課題, 古城幸子,新藤慶,安達雅彦,井関智美,福岡悦子,逸見英枝,芝崎美和,久保田トミ子,矢庭さゆり,神原光,木村靖弘,大嶋信一,小郷敏男, 2011年, 新見公立大学紀要, 32, 55, 60
- 新見公立短期大学附属図書館の利用実態と課題――学生・教員へアンケートを実施して, 逸見英枝,金山時恵,新藤慶, 2010年, 新見公立大学紀要, 31, 161, 170
- 住民運動論の展開からみる地域社会学の動向と課題――1970年代後半~1990年代を中心として, 新藤慶, 2010年, 新見公立大学紀要, 31, 103, 115
- 保育所における絵本を軸とした子育て支援と家庭における絵本体験――岡山県A町を対象として, 新藤慶,高月教恵, 2009年, 新見公立短期大学紀要, 30, 23, 35
- 「社会調査のアーカイブズ学」の必要性――札幌学院大学SORDが取り組んだ「夕張調査資料集成」作成経験からの提言, 中澤秀雄,西城戸誠,大國充彦,新國三千代,祐成保志,新藤慶,小内純子,高橋徹, 2009年, 理論と方法, 45, 121, 128
- 幼保総合施設の実態と課題――認定こども園を扱った諸研究の検討を中心として, 新藤慶, 2008年, 新見公立短期大学紀要, 29, 181, 188
- 市町村合併をめぐる住民投票運動の展開と地域権力構造の変容――群馬県富士見村を事例として, 新藤 慶, 2008年, 現代社会学研究, 21, 1, 17
- 実習後の学生の自己課題の動向――過去5年の幼稚園教育実習事後指導を通して, 高月教恵,新藤慶,片山啓子,安達雅彦,三好年江,堀内秀子,逸見晶子,横見ミヤ子, 2007年, 新見公立短期大学紀要, 28, 133, 140
- 自然再生をめぐるローカル・ガバナンスの論理――釧路湿原自然再生事業を事例として, 新藤 慶, 2007年, 現代社会学研究, 20, 37, 54
- 「昭和の大合併」研究の動向と「平成の大合併」研究の課題, 新藤 慶, 2005年, 地域社会学会年報, 17, 91, 108
- 一般廃棄物処分場建設反対運動の展開と地域権力構造――北海道旭川市の事例を通して, 新藤 慶, 2003年, 地域社会学会年報, 15, 167, 187
- 1. 市町村合併の進展と地域の教育 : 昭和・平成の大合併の比較を通して(II-8部会 【一般部会】地域社会と教育,研究発表II,一般研究報告), 新藤 慶, 2011年, 日本教育社会学会大会発表要旨集録, 63, 136, 137
- 3. 「平成の大合併」と教育施設の統廃合 : 群馬県内の事例を通して(II-8部会 【一般部会】地域社会と教育,研究発表II), 新藤,慶, 2012年10月, 日本教育社会学会大会発表要旨集録, 156, 157
- 1. 「平成の大合併」の進展と公民館 : 学校統廃合との比較を通して(IV-8部会 地域社会と教育(2),研究発表IV), 新藤,慶, 2013年09月, 日本教育社会学会大会発表要旨集録, 336, 337
- アイヌ文化学習の論理と展望 : 地域との関連に注目して(I-3部会 地域社会と教育,研究発表I), 新藤,慶, 2015年09月, 日本教育社会学会大会発表要旨集録, 62, 63
- 書評 梶井祥子編著 『若者の「地域」志向とソーシャル・キャピタル ― 道内高校生1,755 人の意識調査から』 (中西出版,2016 年), 新藤 慶, 2018年, 現代社会学研究, Contemporary Sociological Studies, 31, 0, 51, 56
- 鳥越皓之・足立重和・金菱清編『生活環境主義のコミュニティ分析――環境社会学のアプローチ』, 新藤 慶, 2019年, 社会学評論, Japanese Sociological Review, 70, 2, 181, 182
MISC
- 書評 内田和浩著『参加による自治と創造——新・地域社会論』(日本経済評論社 2019年), 新藤慶, 2021年06月, 地域社会学会年報, 33, 75, 76, 書評論文,書評,文献紹介等
- 外国人児童生徒の動態と学校―家庭連携の可能性——国籍に注目した分析を通じて, 新藤 慶, 2021年02月, 群馬大学共同教育学部紀要 人文・社会科学編, 70, 191, 206
- 外国人の子どもを対象とした貧困研究の成果と教育実践上の課題, 新藤 慶, 2021年03月, 群馬大学教育実践研究, 38, 287, 296, 記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 外国人児童生徒の動態と学校-家庭連携の可能性——国籍に注目した分析を通じて, 新藤 慶, 2021年02月, 群馬大学共同教育学部紀要 人文・社会科学編, 70, 191, 206, 記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 書評 徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子編『地方発 外国人住民との地域づくり——多文化共生の現場から』(晃洋書房 2019年), 新藤慶, 2020年05月25日, 地域社会学会年報, 32, 173, 174
- 書評 梶井祥子編著『若者の「地域」志向とソーシャル・キャピタル——道内高校生1,755人の意識調査から』, 新藤慶, 2018年06月, 現代社会学研究, 31, 51, 56
- 貧困調査のクリティーク(3)――「まなざしの地獄」再考, 宮内洋・松宮朝・新藤慶・石岡丈昇・打越正行, 2018年06月, 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 131, 33, 54
- 中学生からみた尺別炭砿の学校生活と閉山の影響――尺別炭砿中学校23・24・25期生の座談会記録, 新藤慶・嶋﨑尚子・石川孝織・木村至聖・畑山直子・笠原良太, 2019年02月, JAFCOF釧路研究会リサーチ・ペーパー, 14, 1, 48
- アイヌの子どもと教師の関わり――北海道札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町での実態調査から, 新藤慶, 2019年02月, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 68, 141, 156
- 「団体・サークル」活動の意義に関する考察――女性吹奏楽団員への意識調査をもとに, 矢島正・新藤慶, 2019年03月, 群馬大学教育実践研究, 36, 197, 206
- 群馬大学教職大学院の修了生への調査からみられる教職大学院の成果と改善点の検討Ⅳ――面接調査に基づく児童生徒支援能力・学校運営能力の評価, 佐藤浩一・新藤慶, 2019年03月, 群馬大学教育実践研究, 36, 165, 185
- 教職大学院における学修を促進する要因の検討 ―12年間の実践と成果検証を踏まえて―, 山口陽弘・佐藤浩一・新藤慶・山崎雄介, 2020年03月10日, 群馬大学教育実践研究, 37, 255, 265
- 群馬大学教職大学院修了生の「教員としての資質」の現状と課題 ―教員育成指標をふまえた勤務校管理職への調査に基づいて―, 新藤慶・佐藤浩一・田村充, 2020年03月10日, 群馬大学教育実践研究, 37, 239, 254
- 群馬大学教職大学院における小中学校教員の成長 ―学校長との面接に基づく検討―, 佐藤浩一・新藤慶, 2020年03月10日, 群馬大学教育実践研究, 37, 225, 237
- 教育委員会への調査からみられる群馬大学教職大学院の成果と改善点の検討 ― 院生への期待・研究・修了後の評価に着目して ―, 新藤慶・佐藤浩一, 2020年01月31日, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 69, 179, 194, 記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 「ヤマの学校」の思い出, 新藤 慶, 2017年, JAFCOF釧路研究会リサーチ・ペーパー, 10, 59, 70
- 炭鉱閉山がもたらす子どもの生活と意識の変容――尺別炭砿閉山前後の中学生の作文・手紙を通して, 新藤 慶, 2016年, JAFCOF釧路研究会リサーチ・ペーパー, 9, 1-24.
- 地域の意識・行動とアイヌ民族との交流・意識, 新藤 慶, 2016年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 35, 229, 257
- 公民館分館長と地域社会との関係 ― 新潟県佐渡市の事例を通して ―, 新藤 慶, 2016年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 65, 171, 186
- 市町村合併の進展と公民館組織の変容 ― 新潟県佐渡市の事例を通して―, 新藤 慶, 2015年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 64, 115, 134
- 伊達市におけるアイヌ民族・文化の位置づけと評価, 新藤 慶, 2014年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 31, 145, 164
- アイヌ子弟への学習支援活動の利用実態と意識, 新藤 慶, 2014年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 31, 62, 70
- 地域への評価, 新藤 慶, 2013年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 30, 148, 166
- サーミの生活と復権をめぐる運動, 新藤 慶, 2013年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 29, 87, 104
- 学校統廃合研究の動向と今後の課題――2000年以降を中心に, 新藤 慶, 2013年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 62, 125, 137
- 外国籍児童生徒の学びを支える「家庭と学校との関係」構築に向けて ― 在日ブラジル人を中心とする外国籍児童生徒教育の諸研究の振り返りから ―, 新藤 慶, 2018年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 67, 231, 244
- アイヌ民族多住都市におけるアイヌ政策の展開――北海道札幌市の事例を通して, 新藤 慶, 2017年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 66, 183, 197
- フィンランドのサーミ議会の現状と課題, 新藤 慶, 2016年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 34, 17, 26
- アイヌ民族との交流・アイヌ民族に対する意識と地域的要因, 新藤 慶, 2015年, 北海道アイヌ民族生活実態調査報告, 4, 95, 114
- アイヌ民族多住地域としての白糠町への評価, 新藤 慶, 2015年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 33, 211, 229
- 「平成の大合併」と学校統廃合の関連――小学校統廃合の事例分析を通して, 新藤 慶, 2014年, 群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編, 63, 99, 115
- サーミ学校関係者の教育意識, 野崎 剛毅,新藤 慶,新藤 こずえ, 2013年, 『調査と社会理論』・研究報告書, 29, 105, 145
- 公立小中学校における日本人とブラジル人の相互関係と親の意識, 新藤慶,岡田朋子, 2008年, 調査と社会理論・研究報告書, 25, 17, 133
- トメアスー移住地の歴史と現状, 小野寺理佳,新藤慶, 2008年, 調査と社会理論・研究報告書, 26, 43, 48
- トメアスー移住地におけるデカセギと地域社会, 新藤慶, 2008年, 調査と社会理論・研究報告書, 26, 69, 80
- 教育と保育を通じた日本人とブラジル人の関係, 新藤慶,菅原健太,品川ひろみ,野崎剛毅, 2009年, 調査と社会理論・研究報告書, 28, 177, 214
- 僻地農村におけるデカセギの影響, 新藤慶,小野寺理佳,濱田国佑, 2009年, 調査と社会理論・研究報告書, 28, 281, 312
- 浜松市におけるブラジル人託児所の現状と課題, 新藤慶,小野寺理佳, 2009年, 多文化保育研究・研究報告書, 1, 50, 81
- 北海道社会調査データベース作成の理念と方針――SORD新プロジェクトへの方針転換と2年間の活動報告, 中澤秀雄,西城戸誠,新國三千代,大國充彦,森田誠,新藤慶, 2004年, 社会情報, 13, 2, 191, 218
- 産炭都市夕張の社会学的研究――布施鉄治編『地域産業変動と階級・階層』の知識社会学的検討を中心として, 新藤慶, 2005年, 社会情報, 14, 2, 319, 331
- 調査サンプルの構成, 新藤慶, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 15, 21
- 労働上の課題と諸機関や人々の役割, 新藤慶, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 22, 46
- 健康上の問題と諸機関・人々の役割, 新藤慶, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 70, 83
- 社会各層と政治・社会意識, 新藤慶, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 110, 122
- 山村留学の歴史と現状, 安宅仁人,新藤慶,濱田国佑, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 197, 208
- 教師の教育実践と山村留学の評価, 新藤慶, 2005年, 発達・学習支援ネットワーク研究, 2, 220, 239
- 廃棄物処分場の集積と地域住民の対応――北海道旭川市を事例として, 新藤慶, 2003年, 北海道大学大学院教育学研究科紀要, 91, 135, 161
- 知立市における多文化保育の現状, 品川ひろみ,新藤慶, 2011年, 多文化保育研究・研究報告書, 2, 61, 111
- 「平成の大合併」の展開と地域社会の教育への影響に関する一試論――合併に伴う住民の学習過程の分析を中心として, 新藤 慶, 2012年, 群馬大学教育学部紀要人文・社会科学編, 61, 171, 187
- 地域住民の学習過程の教育社会学的分析方法――松原治郎グループの研究を中心として, 新藤 慶, 2011年, 人文科学論叢, 6, 9, 20
- 貧困調査のクリティーク(2)――『排除する社会・排除に抗する学校』から考える, 宮内 洋,松宮 朝,新藤 慶,石岡 丈昇,打越 正行, 2015年, 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 122, 49, 91
- 新たな貧困調査研究の構想のために――日本国内の貧困研究の再検討から, 宮内 洋,松宮 朝,新藤 慶,石岡 丈昇,打越 正行, 2014年, 愛知県立大学教育福祉学部論集, 62, 123, 135
- 貧困調査のクリティーク(1)――『豊かさの底辺に生きる』再考, 宮内 洋,松宮 朝,新藤 慶,石岡 丈,打越 正行, 2014年, 北海道大学大学院教育学研究院紀要, 120, 199, 230
書籍等出版物
- 芦別: 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史, 分担執筆, 嶋﨑尚子,西城戸誠,長谷山隆博(以上編著),笠原良太,坂田勝彦,島西智輝,清水拓,新藤慶,中澤秀雄, 第9章「炭鉱町から地方都市へ――戦後芦別市の地域産業構造と社会移動の変遷」(PP.234-256),コラム11「芦別支店,芦別営業所,芦別鉱業所」(PP.257-258),第10章「芦別で働いた人たち――芦別出身者と転入者の比較を通して」(PP.259-274), 寿郎社, 2023年12月
- 〈生活-文脈〉理解のすすめ: 他者と生きる日常生活に向けて, 共著, 宮内洋・松宮朝・新藤慶・打越正行, 第3章「成人期の政治行動をとおして考える〈生活-文脈〉理解: 市町村合併の事例から」, 北大路書房, 2024年05月, 81-119
- 戦後日本の出発と炭鉱労働組合:夕張・笠嶋一日記 1948~1984年, 共著, 中澤秀雄・新藤慶・西城戸誠・玉野和志・大國充彦・久保ともえ, 「公民館運動と青年社会教育」、1948年日記解説, 御茶の水書房, 2022年10月, ISBN: 978-4-275-02167-0
- 外国につながり子どもの学びを支える教育・保育機関と家庭の連携の実態と展望: 群馬県大泉町を対象と して, 編者(編著者), 新藤慶編(新藤慶・野崎剛毅・品川ひろみ・上山浩次郎・濱田国佑・小野寺理佳), 群馬大学共同教育学部学校教育講座新藤研究室, 2022年03月, 139
- 国文学科主催シンポジウム記録2020 自己を物語る―文学の中の社会、社会の中の文学をライフストー リーから考える―,国文学科主催シンポジウム記録2021 他者と語り合う―在住外国人の日本語から考え る―, 共著, 群馬県立女子大学文学部国文学科編(好井裕明・安保博史・宮内洋・川口直巳・新藤慶), 群馬県立女子大学文学部国文学科, 2022年03月, 78, 41-76
- 子ども家庭福祉——子ども・家族・社会をどうとらえるか, 分担執筆, 垣内国光・岩田美香・板倉香子・新藤こずえ・小西祐馬・関水徹平・井原哲人・菅野摂子・尾島万里・飯塚美穂子・宮地さつき・新藤慶・澁谷智子・川松亮・大澤真平・堀千鶴子・福間麻紀, 「コラム3 外国籍の子どもと家族への対応」, 生活書院, 2020年12月, 297, 139-140, 教科書・概説・概論
- 〈つながり〉の戦後史——尺別炭鉱閉山とその後のドキュメント, 共著, 嶋﨑尚子・新藤慶・木村至聖・笠原良太・畑山直子, 「第6章 炭鉱コミュニティの『暮らし』——尺別の地縁の多層性」「コラム4 看護婦として、炭鉱とともに——宗村達江さんインタビュー」「第10章 『地縁』のゆくえ——同郷団体にみる新たな〈つながり〉」「コラム6 東京にも尺別の絆をつなぐ——菖蒲隆雄さんインタビュー」「おわりに」, 青弓社, 2020年11月, 267, 104-119,192-196,204-218,248-252,259-263, 学術書, ISBN: 978-4-7872-3477-3
- シリーズ子どもの貧困3 教える・学ぶ――教育に何ができるか, 分担執筆, 佐々木宏・堅田香緒里・桜井啓太・丸山啓史・新藤慶・鳥山まどか・篠原岳司・中澤渉・盛満弥生・金澤ますみ・西牧たかね・岡本実希, 外国につながる子どもの貧困と教育, 明石書店, 2019年04月, 105-128
- 先住民族の社会学1 北欧サーミの復権と現状――ノルウェー・スウェーデン・フィンランドを対象にして, 第7章 スウェーデン・サーミの生活実態とエスニック・アイデンティティ, 東信堂, 2018年, 346, 163-188
- 先住民族の社会学2 現代アイヌの生活と地域住民――札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして, 第1章 地域におけるアイヌの歴史と自治体のアイヌ政策, 東信堂, 2018年, 322, 26-48
- 炭鉱労働の現場とキャリア――夕張炭田を中心に【第2版】, 産炭地研究会, 2016年
- スウェーデン・サーミの生活と意識――国際郵送調査からみるサーミの教育、差別、民族・政治意識、メディア, 札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科, 2015年
- 炭鉱労働の現場とキャリア――夕張炭田を中心に, 産炭地研究会, 2014年
- スウェーデンにおける世代間の育児支援, 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科, 2014年
- 住民の視点から見た市町村合併の展開過程と合併後の状況――岡山県新見市の事例を通して, 群馬大学教育学部学校教育講座教育社会学研究室, 2013年
- 市町村合併の展開過程における住民の行動と意識――群馬県榛名地区を事例として, 群馬大学教育学部学校教育講座教育社会学研究室, 2011年
- 新版 キーワード地域社会学, 「生活圏/通勤圏/購買圏」「住民運動・市民運動」, ハーベスト社, 2011年, 401, 182-3, 350-1, ISBN: 9784863390287
- 「世代間の育児支援」からみた祖父母とその子世代の関係, 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科, 2011年
- 北海道における社会調査の水脈――戦後復興期から1970年代まで, 札幌学院大学SORDプロジェクト, 2010年
- 市町村合併をめぐる住民の意識と関わり――群馬県富士見地区を事例として, 新見公立短期大学幼児教育学科教育学研究室, 2010年
- 講座 トランスナショナルな移動と定住――定住化する在日ブラジル人と地域社会 第2巻 在日ブラジル人の教育と保育の変容, 新藤慶・菅原健太・濱田国佑・菊地千夏・品川ひろみ・野崎剛毅・上山浩次郎・小内透・都築くるみ, 「第1章 公立学校に通うブラジル人児童生徒と保護者の生活と意識」「第4章 公立小中学校における日本人と外国人」(菅原健太と共著), 御茶の水書房, 2009年, 210, 3-34, 103-35
- 講座 トランスナショナルな移動と定住――定住化する在日ブラジル人と地域社会 第3巻 ブラジルにおけるデカセギの影響, 飯田俊郎,アンジェロ・イシ,小内透,小野寺理佳,新藤慶,濱田国佑,品川ひろみ,野崎剛毅, 「第4章 僻地農村におけるデカセギの影響」(小野寺理佳・濱田国佑と共著), 御茶の水書房, 2009年, 189, 91-130
- 「夕張調査」資料集成――布施鉄治編『地域産業変動と階級・階層』(1982)調査関係資料コレクション, 札幌学院大学社会情報学部SORDデータアーカイブ, 2009年
- 自然再生をめぐるローカル・ガバナンスの現状と課題――釧路湿原自然再生事業の事例を通して, 北海道大学大学院法学研究科学術創成プロジェクト事務局, 2006年
- 野幌とはどのような場所か――その生活史と地区形成, 札幌学院大学社会情報学部社会情報調査室, 2004年
- 在日ブラジル人の教育と保育――群馬県太田・大泉地区を事例として, 小内透・小野寺理佳・古久保さくら・新藤慶・濱田国佑・野崎剛毅・品川ひろみ・飯田俊郎, 「第5章 太田・大泉地区のブラジル人学校」「第8章 ブラジル人学校教師の生活と教育意識」「第10章 認可保育所の実態と保育士の意識」(第10章は品川ひろみ・小野寺理佳と共著), 明石書店, 2003年, 230, 82-93, 124-38, 167-82
講演・口頭発表等
- 共同教育学部における斉一授業の成果と課題――宇都宮大学・群馬大学の事例から, 新藤慶・鈴木豪・河内昭浩・佐野史・佐々木和也・丸山剛史・川島芳昭・伊藤明彦, 令和6年度日本教育大学協会研究集会, 2024年09月28日, 日本語, 群馬大学
- 外国につながる子どもの困難と地域社会の新たな関係: 子どもの日本語能力と進路保障をめぐる地域社会の現状を通して, 新藤慶, 地域社会学会第48回大会, 2023年05月14日, 日本語, 駒澤大学(東京)
- 「在留外国人の子どもの教育からみた多文化共生社会: 在日ブラジル人の子どもを中心に, 新藤慶, 第69回北海道社会学会大会, 2021年06月21日, オンライン(札幌国際大学)
- ‘Regional Bond’ in Coalfield Community : A Case Study of Shakubetsu Colliery, Kei SHINDO, Coal Mining History and Heritage in the UK and Japan : Workshop 2, 2019年12月
- 産廃施設建設反対運動の「停滞」局面に関する一研究――北海道鷹栖町の事例におけるリーダー層の学習過程に着目して, 日本社会教育学会・日本教育社会学会第24回東北・北海道研究集会, 2000年
- 一般廃棄物処理施設建設に対する住民運動の構造に関する実証的研究――「自区内処理原則」と「参加型住民自治組織」と手掛かりとして, 第49回北海道社会学会大会, 2001年
- 一般廃棄物処分場建設反対運動の展開と地域権力構造――北海道旭川市の事例を通して, 第27回地域社会学会大会, 2002年
- 「環境運動」と「住民自治」としての廃棄物処分場建設反対運動――北海道旭川市の事例を通して, 日本社会教育学会・日本教育社会学会第26回東北・北海道研究集会, 2002年
- ブラジル人学校の教育と父母の意識, 日本教育社会学会第54回大会, 2002年
- 廃棄物処分場建設反対運動の展開と運動戦術をめぐる葛藤――北海道旭川市の事例から, 日本社会教育学会・日本教育社会学会第27回東北・北海道研究集会, 2003年
- 市町村合併研究の動向と課題, 第52回北海道社会学会大会, 2004年
- 地域住民の生活課題とネットワークの役割――北海道十勝管内士幌町の調査から, 日本社会教育学会・日本教育社会学会第29回東北・北海道研究集会, 2005年
- 地域に支えられた山村留学――北海道十勝管内士幌町立下居辺小学校の事例から, 日本社会教育学会・日本教育社会学会第29回東北・北海道研究集会, 2005年
- 北海道における「社会調査の社会調査」を目指して(1)――リージョン拠点データアーカイブの意義, 第53回北海道社会学会大会, 2005年
- 北海道における「社会調査の社会調査」を目指して(2)――夕張データセットの多次元的解読に向けて, 第53回北海道社会学会大会, 2005年
- 北海道における「社会調査の社会調査」を目指して(3)――北海道社会調査データベースの利用可能性, 第53回北海道社会学会大会, 2005年
- 法定協議会設置後の合併協議の「破談」とその要因――群馬県富士見村の事例を通して, 第31回地域社会学会大会, 2006年
- 市町村合併をめぐる住民投票運動と運動従事者の生活――群馬県富士見村の事例を通して, 第55回北海道社会学会大会, 2007年
- 公立小中学校におけるブラジル人と日本人の関係――集住地間の比較分析を通して, 日本教育社会学会第60回大会, 2008年
- 市町村合併をめぐる住民の意志と関わり――群馬県富士見村・旧榛名町の事例を通して, 第34回地域社会学会大会, 2009年
- 市町村合併と住民の意識変容――群馬県旧富士見村・旧榛名町の事例を通して, 日本教育社会学会第61回大会, 2009年
- 戦後北海道における社会調査史の再構成とデータアーカイブの構築(3)――布施鉄治の労働-生活過程の社会調査史, 第83回日本社会学会大会, 2010年
- 昭和・平成の大合併と地域社会の変容, 地域社会学会2010年度第4回研究例会, 2011年
- 「平成の大合併」と教育施設の統廃合: 群馬県内の事例を通して, 日本教育社会学会第64回大会, 2012年
- 産炭地の比較社会学Ⅱ-(1)――布施調査の意義/限界と夕張炭田, 第85回日本社会学会大会, 2012年
- 市町村合併の進展と地域の教育――昭和・平成の大合併の比較を通して, 日本教育社会学会第63回大会, 2011年
- 市町村合併と住民の労働-生活圏――群馬県内の事例の比較を中心に, 第84回日本社会学会大会, 2011年
- アイヌ文化学習の論理と展望――地域との関連に注目して, 日本教育社会学会第67回大会, 2015年
- スウェーデン・サーミの生活と意識(2)――サーミの政治・社会意識, 第87回日本社会学会大会, 2014年
- 「平成の大合併」の進展と公民館――学校統廃合との比較を通して, 日本教育社会学会第65回大会, 2013年
- 市町村合併と公民館組織の変容――新潟県佐渡市の事例を通して, 地域社会学会第39回大会, 2014年
- 公立学校におけるブラジル人保護者と教師との関係――群馬県大泉町における教師調査から, 日本教育社会学会第69回大会, 2017年
- 群馬大学教職大学院の修了研究における個別指導と、実習校との連携体制――「課題解決実習」・「課題研究」の二年間のプロセスを通して, 平成28年度日本教職大学院協会研究大会, 2016年
- 子どもの貧困:沖縄における若年層をもとに, 日本子ども社会学会第23回大会, 2016年
- アイヌの人々の学校経験――アイヌの人々と教師との関わりに注目して, 日本教育社会学会第68回大会, 2016年
- 社会調査からみる戦後北海道教育の展開と特質――北海道社会調査データベースをもとにして, 第66回北海道社会学会大会, 2018年
受賞
- 地域社会学会賞(共同研究部門), 嶋﨑尚子・西城戸誠・長谷山隆博編『芦別――炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(寿郎社、2023年)に対して, 2025年05月, 国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 地域社会学会賞(共同研究部門), 地域社会学会, 小内透編『先住民族の社会学第 2 巻 現代アイヌの生活と地域住民』(東信堂,2018年)に対して
- 地域社会学会賞(共同研究の部門), 2011年
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 住民運動における地域住民の学習過程, その他の研究制度, 競争的資金
- 市町村合併に伴う地域社会の共同性の変容, 科学研究費補助金, 競争的資金
- 在日ブラジル人の教育と保育, 科学研究費補助金, 競争的資金
- Residents' Learning Processes in Residential Movements, The Other Research Programs, 競争的資金
- Change of Communarity in Local Community Caused by Municipal Merger, Grant-in-Aid for Scientific Research, 競争的資金
- Education and Childcare of Brazilian Children in Japan, Grant-in-Aid for Scientific Research, 競争的資金
学術貢献活動
社会貢献活動情報
社会貢献活動
- 外国にルーツをもつ生徒・保護者の理解と対応――多文化共生の視点から, 群馬県教育委員会, 令和6年度第3回公立高等学校・公立中等教育学校・県立特別支援学校等副校長・教頭研究協議会, 2025年01月09日(対象:教育関係者)
- 地域の国際化と多文化共生社会の構築――群馬県西部地区の状況をもとに, 群馬県教育委員会西部教育事務所, 令和6年度西部地区人権教育指導者研修会, 2024年10月24日(対象:教育関係者, 行政機関)
- 前橋市男女共同参画審議会委員(副会長)(対象:行政機関)
- 富岡市教育委員会点検・評価委員(対象:教育関係者, 行政機関)
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2024年07月02日(対象:高校生)
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2024年05月30日(対象:高校生)
- 富岡市教育委員会点検・評価委員, 2020年02月, 9999年
- 前橋市男女共同参画審議会委員, 2019年07月, 9999年
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2023年11月20日, 2023年11月20日(対象:高校生)
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2023年10月19日, 2023年10月19日, 出前授業(対象:高校生)
- 富岡市教育委員会点検・評価委員, 2023年03月16日(対象:教育関係者)
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2022年11月21日, 高崎健康福祉大学高崎高等学校, 出前授業(対象:高校生)
- 現代社会の教育問題: その実態と解決の展望, 2022年11月08日, 群馬県立太田東高等学校, 出前授業(対象:高校生)
