研究者データベース
| 宮崎 沙織 | 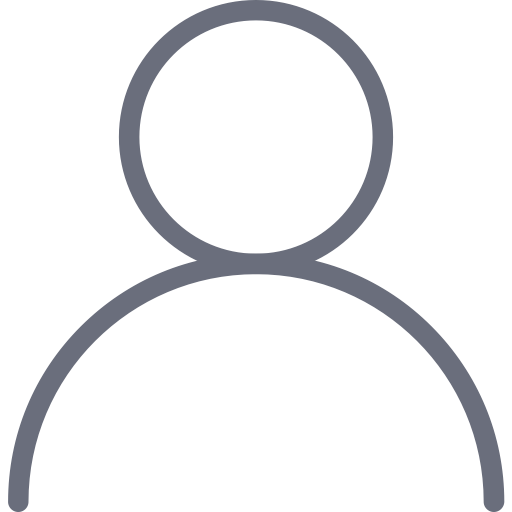 |
| ミヤザキ サオリ | |
| 社会科教育講座 | |
| 准教授 | |
Last Updated :2025/05/30
研究者基本情報
研究者
氏名
宮崎 沙織, ミヤザキ サオリ
所属
基本情報
研究者氏名(日本語)
宮崎, 沙織研究者氏名(カナ)
ミヤザキ, サオリ
論文上での記載著者名
所属
所属部局等
所属情報
共同教育学部, 社会科教育講座
学位
所属学協会
経歴
研究活動情報
研究分野
研究キーワード
論文
- 中等地理教育で中心市街地のあり方を考えるための地域学習単元開発 ―歴史地理学研究との共同開発の試み―, 宮崎沙織、関戸明子、今井貴秀, 2020年03月10日, 群馬大学教育実践研究, 37, 15, 31
- 小学校社会科における社会的な態度を育てる授業と学習評価のデザイン ―外部人材を活用し、実社会とつなげた単元モデルの提案―, 根岸愛美、宮崎沙織, 2025年03月01日, 群馬大学教育実践研究, 42, 33, 45
- システムアプローチで考える地理教育(第2回)英米独の地理教育におけるシステムアプローチ, 山本 隆太,梅村 松秀,宮崎 沙織,泉 貴久, 2018年, 地理, 63, 3, 104-109
- システムアプローチで考える地理教育(第1回)システムアプローチとは, 梅村 松秀,泉 貴久,山本 隆太,宮﨑 沙織, 2018年, 地理, 63, 2, 106-110
- 小学校社会科における地域分析による“位置や空間的な広がりの視点”の構造化 ― 群馬県板倉町と嬬恋村を事例とした単元開発 ―, 宮崎 沙織,青山 雅史,関戸 明子, 2018年, 群馬大学教育実践研究, 35, 1-15.
- 米国の環境教育推進における社会科系教科の役割, 宮崎 沙織, 2014年, 群馬大学教科教育学研究, 13, 19-28
- システムアプローチで考える地理教育(第13回)「社会構造やパラダイムに気づくことの重要性」, 宮崎沙織, 2019年02月, 地理, 64, 2月号, 110-115
- 小学校社会科における「防災」, 宮崎沙織, 2018年10月, 東書教育シリーズ 小学校社会科教授用資料 新学習指導要領と現代的な諸課題, 10-13
MISC
- システムアプローチで考える地理教育(第2回)英米独の地理教育におけるシステムアプローチ, 山本 隆太,梅村 松秀,宮﨑 沙織,泉 貴久, 2018年03月, 地理, 63, 3, 104, 109
- システムアプローチで考える地理教育(第1回)システムアプローチとは, 梅村 松秀,泉 貴久,山本 隆太,宮﨑 沙織, 2018年02月, 地理, 63, 2, 106, 110
- 〈研究論文〉 アメリカ社会科における環境リテラシーの構造 : 北米環境教育連盟ガイドラインの分析を通して, 宮崎 沙織,Saori Miyazaki, 2012年03月31日, 中等社会科教育研究 = Secondary social studies, 30, 1, 13
- システムアプローチを活用した地域学習の在り方 (2019年1月例会報告), 宮崎 沙織, 2019年08月, 新地理 = The new geography, 67, 2, 38, 40
- システムアプローチで考える地理教育(第13回)社会構造やパラダイムに気づくことの重要性, 宮﨑 沙織, 2019年02月, 地理, 64, 2, 110, 115
- 米国の環境教育推進における社会科系教科の役割, 宮崎 沙織, 2013年, 群馬大学教科教育学研究, 13, 19, 28
- 沖縄県小浜島における地域行事と子どもの地域認識 : 伝統・文化の側面から, 宮崎 沙織, 2006年12月25日, 新地理 : 日本地理教育學會會誌, 54, 3, 81, 81
- カナダ ブリティッシュ・コロンビア州における環境学習の展開:環境倫理を中心とした学習内容の転換, 宮崎 沙織, 2008年, 社会科教育研究, The Journal of Social Studies, 2008, 104, 86, 97
- カリフォルニア州における環境リテラシー育成のための社会科プログラム:環境の原理に基づく学習内容の再構成に着目して, 宮崎 沙織, 2009年, 社会科教育研究, The Journal of Social Studies, 2009, 108, 58, 69
- 小学校社会科における地域分析による“位置や空間的な広がりの視点”の構造化 ― 群馬県板倉町と嬬恋村を事例とした単元開発 ―, 宮崎 沙織,青山 雅史,関戸 明子, 2018年, 群馬大学教育実践研究, 35, 1-15.
書籍等出版物
- 社会問題の解決を目指す地理教育:システム思考からさらにその先へ, 編者(編著者), 学文社, 2025年03月, 211, ⅰ-ⅵ, 162-179, ISBN: 9782762034176
- Well-beingをめざす社会科教育:人権/平和/文化多様性/国際理解/環境・まちづくり, 分担執筆, 井田仁康監修、唐木清志・國分麻里・金ヒョン辰編著、宮﨑沙織他24名著, 5-1 地理教育として環境問題をどう扱うかーカナダ・オンタリオ州の中等地理科目改訂を手がかりにー, 古今書院, 2024年04月23日, 308, 236-245, 学術書
- 社会科の「問題解決的な学習」とは何か, 分担執筆, 唐木清志編著宮崎沙織他11名著, 第Ⅱ章第1節社会や環境に関わる課題の解決志向型の社会科学習の提案, 東洋館出版社, 2023年07月23日, 166, 26-35, 学術書
- 実践・小学校社会科指導法, 分担執筆, 澤井陽介、中田正弘編、宮﨑沙織その他9名, 2.2「地理的環境と人々の生活」に関する内容とその指導、9地図、地図帳、地球儀の使い方, 2021年02月, 15-18、87-97
- 初等社会科教育, 分担執筆, 清水 美憲,小山 正孝監修、唐木清志,永田忠道編著、宮﨑沙織、その他, 社会科における調査・見学のあり方について 述べなさい、社会科における地図帳の活用法について述べ なさい, 2021年06月, 66-68,78-80
- 社会科における多文化教育――多様性・社会正義・公正を学ぶ, 分担執筆, 森茂岳雄、川﨑誠司、桐谷正信、青木香代子編、宮﨑沙織、その他12名, 地理教育における多様性の学び方, 明石書店, 2019年06月, 81-94
- システム思考で地理を学ぶー持続可能な社会づくりのための授業プランー, 編者(編著者), 地理教育システムアプローチ研究会編, 山本 隆太, 阪上 弘彬, 泉 貴久, 梅村 松秀, 河合 豊明, 中村 洋介, 宮﨑 沙織, 社会構造やパラダイムに気づかせよう, 古今書院, 2021年03月, 7-12
- 社会を創る市民の教育ー協同によるシティズンシップ教育の実践, 東信堂, 2016年
- 『21世紀の教育に求められる 社会的な見方・考え方』, 帝国書院, 2018年
講演・口頭発表等
- 持続可能な社会の創り手を育てる社会科授業づくりへの第一歩, 宮崎沙織, 全小社研令和7年度群馬大会プレ大会(令和6年度開催), 2024年11月15日, 2024年11月15日
- 社会問題の解決を目指す「解決志向型」の地理学習の実践に向けて―システム思考を基盤とした取り組みからの提案―, 宮﨑沙織・佐藤真久・阪上弘彬・中村理恵・山本隆太, 日本地理教育学会第74回大会, 2024年08月25日
- 小学校社会科における外部人材を活用した主体的に学習に取り組む態度を高める授業デザイ ン, 根岸愛美・宮崎沙織, 日本社会科教育学会第73回全国研究大会, 2023年10月29日
- 現代社会の諸課題の解決志向型による小学校社会科学習の提案―第4学年「県内の特色ある地域」を事例として―, 宮崎沙織・根岸愛美, 群馬地理学会, 2023年11月11日
- 日本の中等地理教育における地球的課題に関する学習指導の特徴と課題-システマティックレビュー-, 阪上弘彬, 宮﨑沙織, 山本隆太, 日本社会科教育学会, 2022年10月22日, 2022年10月22日, 2022年10月23日, 信州大学
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 地球的課題の解決志向型中等地理カリキュラムに関する理論的実践的研究, 2020年, 2024年
- アメリカ・カナダ社会科における多文化教師教育に関する研究, Research on multicultural teacher education in the United States Canadian social studies, 桐谷 正信,宮崎 沙織,坪田 益美, KIRITANI Masanobu,MIYAZAKI Saori,TSUBOTA Masumi, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 埼玉大学, Saitama University, 2011年, 2013年, 本研究では,国内の多文化化・価値の多様化の進展に伴う教育の課題に応えるために,アメリカ及びカナダおける多文化教育を実践する多文化教師教育のあり方について考究する基礎的研究を行った。 グローバル人材の育成として注目される国際バカロレアでは,教員免許取得や研修においても,多文化を肯定的に受容し,積極的に活用していく能力・態度の育成が求められる。また,教師教育を行う高等教育機関におけるマイノリティに対する差別が,多文化教育を実践できる教師の育成を阻害する主要な要因であることが明らかになった。, It is a fundamental study on the ideal way of the multi-cultural teacher education that practices the multicultural instruction that kicks the United States and Canada because it answers the problem of the education according to the progress of the diversification of a domestic cultural diversification and value. The promotion of the ability and the attitude that affirmatively receives various cultures, and uses it positively is requested in the teacher's license acquisition and training in the international baccalaureat paid attention to as a promotion of global talent. Moreover, discrimination in the higher education organization that educates the teacher to the minority is the main factor to obstruct the promotion of the teacher who can practice the multicultural instruction., 23531160
- 交通環境学習における社会的ジレンマ教材の開発, Teaching Materials of Social Dilemma in Traffic-Environment Learning, 唐木 清志,水山 光春,吉村 功太郎,磯山 恭子,宮崎 沙織,藤井 聡,松村 暢彦,谷口 綾子,梅澤 真一,大山 喜裕,岩本 知之,早馬 忠弘,岩坂 尚史,岡田 泰孝,寺本 誠, KARAKI Kiyoshi,MIZUYAMA Mitsuharu,YOSHIMURA Kotaro,ISOYAMA Kyoko,MIYAZAKI Saori,FUJII Satoshi,MATSUMURA Nobuhiko,TANIGUCHI Ayako,UMEZAWA Shinichi,OYAMA Yoshihiro,IWAMOTO Tomoyuki,HAYAMA Tadahiro,IWASAKA Naoshi,OKADA Yasutaka,TERAMOTO Makoto, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 基盤研究(B), Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 筑波大学, University of Tsukuba, 2011年04月01日, 2014年03月31日, 本研究の成果は、現代社会における「交通環境学習」の役割を明確にするとともに、今後学校教育に交通環境学習を導入するにあたり重要な役割を担うであろう「社会的ジレンマ教材」の開発原理を明らかにしたことである。具体的には、第一に、交通環境学習の多様性を示せたことである。第二に、社会的ジレンマが単元開発の一視点となることを示せたことである。第三に、学際的な共同研究により、授業研究の高度化が期待できることを示せたことである。, The result in this research is that we have made clear of a role of "traffic-environment learning" in modern society and a developmental principle of "materials on social dilemma". We think that "materials on social dilemma" can take a important role when teachers will practice "traffic-environment learning" in their classes. Our research have concretely made clear the following three things. First, teachers can practice "traffic-environment learning" in various subjects and fields. Second, social dilemma can become a perspective of unit development. Third, interdisciplinary joint research can promote improvement of the study of class in schools., 23330250
- アメリカ・カナダ社会科における多文化的シティズンシップ育成の理論的・実践的研究, Theories and Practices of the social studies for Multicultural Citizenship in the United States and Canada, 桐谷 正信,坪田 益美,宮崎 沙織, KIRITANI Masanobu,TSUBOTA MASUMI,MIYAZAKI Saori, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 埼玉大学, Saitama University, 2008年, 2010年, アメリカとカナダにおける多文化的社会科教育論と「多様性」・「統一性」の両者に尊重したカリキュラムや教科書の分析を通して,アメリカ・カナダともシティズンシップ教育では,「活動的市民」,「活動的な貢献者」の育成を視野に入れた「良識ある市民」を育成することが必要であり,その「良識あるシティズンシップ」は,社会の「多様性」と「統一性」の両者を尊重した多文化的シティズンシップであることことを明らかにした。, Through analyzing the theories of multicultural social studies education, the curriculums and the textbooks which are respecting both "diversity" and "unity" in the United States and Canada, this study clarified following. first, both of the United States and Canada, in the citizenship education, it is necessary that foster "informed citizen" which is including "active citizen" and "active contributor". And second, the "informed citizenship" is the Multicultural citizenship which is respecting both "diversity" and "unity" of society., 20530802
- 人口減少社会における多文化的社会科教育に関する国際比較研究, 桐谷 正信,坪田 益美,佐藤 公,宮崎 沙織, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 埼玉大学, Saitama University, 2017年04月01日, 2020年03月31日, カナダ・トロント大学にあるオンタリオ教育研究所(OISE:Ontario Institute for Studies in Education)にて,カナダの社会科カリキュラムや教科書,教材,教師用指導書などどの資料の収集及び教材開発についての情報収集を行った。特に,カナダの社会科においてCitizenship EducationとMulticultural Citizenshipの関係を中心に検討した。 2000年以降,カナダ全州の教育省がCitizenshipの育成を強調した社会科への改訂や新教科・科目の導入など,Citizenship Educationへの取り組みが改めて盛んになっている。そこでは,Taylor, C. (1993)の提唱する「アイデンティフィケーションの極(pole)の多元性」を承認し,「国家への所属の仕方の多元性をも承認し受容する」Citizenship Education Educationが展開されている。しかし,連邦政府がMulticulturalsimを掲げている一方,フランス系移民が多数を占めるケベック州だけはMulticulturalsimに対しては批判的である。ケベック州が主張するのはInterculturalismである。ケベック州はいわばCultural Pluralismに近いカナダのMulticulturalsimには背を向け,マジョリティの文化を上位に置いた上で,その他のすべての文化をできる限り尊重するようaccommodation(調整)し続けることを志向する,Interculturalismを志向している。 Multicultural EducationとIntercultural Educationの両者の拮抗とバランスについて検討することが,今後の研究課題である。, 17K04746
- 社会科環境リテラシー育成カリキュラムの構築に関する研究, The Curriculum Development for Environmental Literacy in Social Studies, 宮崎 沙織, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 若手研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B), 若手研究(B), Grant-in-Aid for Young Scientists (B), 群馬大学, Gunma University, 2014年04月01日, 2019年03月31日, 本研究では、アメリカ合衆国の環境リテラシー論を導入した社会科の新しい環境学習カリキュラムを構築することを目的としている。環境リテラシーとは、知識・スキル・感性・行動を含めた環境教育で獲得すべき目標概念のことを指す。 最終年度にあたる本年度は、中等社会科における環境リテラシー育成のフレームワークの提案を行った。特に、中等地理教育における地域学習や現代社会の諸課題学習を中心とし、自然環境との共生・調整を目指した社会科教育のあり方を考察した。 中等段階では、環境リテラシー育成のために、社会構造やパラダイムを把握することや、地域の諸課題解決に主眼を置いた取り組みが中心となることを明らかにした。地理教育では、場所で生じている問題に着目し、その事象がどのように社会構造と関連しているのかを考察することで、問題が生じている背景としての社会構造を把握し、それを解決するための新たな社会構造の在り方を思考することの重要性をしめした。特に、地理教育で環境リテラシーを育成するためには、場所の特性を追究することが重要である。問題が生じている場所の追究を行うことで、自然環境と共生できない社会構造を把握し、共生を目指した社会構造に調整をはかれるような解決策を考えることが、環境リテラシー学習として重視されるのである。 以上を通して、日本の社会科環境リテラシー学習は、自然環境との共生・調整を目指し、自然環境と人間社会との関係性を読み解き、社会構造の在り方を考えることを通し、実践していくことを最終結論とした。今後の課題としては、環境リテラシー学習について、実証的に検証していくことが必要である。そのためにも、各校種の実践校との連携が求められる。, 26780491
- アメリカ・カナダ・ドイツにおける多文化的社会科教育の比較研究, A comparative study of multicultural social studies education in the United States, Canada, Germany, 桐谷 正信,坪田 益美,佐藤 公,宮崎 沙織, KIRITANI Masanobu, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 埼玉大学, Saitama University, 2014年04月01日, 2017年03月31日, 本研究では,アメリカ,ドイツを中心に多文化社会科教育における博物館活用のあり方に着目し,検討を行った。アメリカとドイツの多文化的社会科教育における博物館活用の共通点としては,多様な学習者の文化的背景への配慮から多言語での解説が可能なようにICT機器の活用が積極的に進められている点が挙げられる。相違点としては,アメリカでは展示における学習のストーリーが用意されているのに対し,ドイツでは構成主義的な展示により,学習者の主体的な解釈による学習が可能となるよう配慮されている点が挙げられる。両国とも,学校教育における博物館活用が積極的に推進され,多様な社会的文脈における多文化教育が展開されている。, We focused on the way of utilization of museums in multicultural social studies education, mainly in the United States and Germany. As a common point in utilizing museums in multicultural social studies education in the United States and Germany, it is utilizing ICT equipment so that it can explain in multiple languages from consideration of the cultural background of diverse learners. As a difference, in the United States, a story of learning in the exhibition is prepared, whereas in Germany there is a point that consideration is made so that it can be learned by subjective interpretation of the learner by constructiveistic exhibition . In both countries, utilization of museums in school education has been actively promoted, and multicultural education in various social contexts has been developed., 26381176
- 環境リテラシー学習の理論と方法に関する研究, Research on theory and practice of learning for environmental literacy, 宮崎 沙織, MIYAZAKI Saori, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 若手研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B), 若手研究(B), Grant-in-Aid for Young Scientists (B), 2011年, 2013年, 本研究では、日本型の環境リテラシー学習構築のための研究成果として、次の三点を挙げる。まず、環境リテラシーは、①社会政治的知識、②人間社会と自然環境の相互依存の知識、③行動方略スキル、④個人・市民の責任の四要素を有していることである。次に、環境リテラシーを導入した社会科カリキュラム作成のためには、I地理的な知識内容、IIスキル関連目標、III市民参加・行動に関わる内容を充実させる必要があることだ。そして最後に、環境のとらえを自然システム中心型からヒューマン・エコロジー型に改変し、上記のことを踏まえた単元開発を行うことが重要であることを示した。, The three main findings are shown in this research to contribute to constructing the learning for environmental literacy in Japan. First, it is important to respect sociopolitical knowledge, knowledge of human/environment interactions, skills for action strategy, and personal and civic responsibility as the essential components of environmental literacy.Second, environmental literacy can be effectively introduced into social studies curriculum by valuing geographical knowledge, skill-related objectives, and civic participation and actions.Third, it is important to change the point of view for recognizing environment from natural system-centered to human ecology-centered and develop learning units based on this idea to construct learning for environmental literacy in Japan., 23730822
社会貢献活動情報
学術貢献活動
- 日本地理教育学会編集委員会委員, 学会・研究会等, 2022年, 2024年
- 全国社会科教育学会第71回全国研究大会シンポジウムコメンテーター, 大会・シンポジウム等, 全国社会科教育学会, 2022年10月08日
- 日本社会科教育学会研究推進委員, 学会・研究会等, 日本社会科教育学会, 2022年04月01日, 2024年03月31日
- 日本社会科教育学会国際交流委員, 学会・研究会等, 日本社会科教育学会, 2020年04月01日, 2022年03月31日
- 日本社会科教育学会編集委員, 学会・研究会等, 日本社会科教育学会, 2020年04月01日, 2022年03月31日
- 日本地理教育学会集会専門委員, 学会・研究会等, 日本地理教育学会, 2019年04月01日, 2022年03月31日
