研究者データベース
| 益田 裕充 | 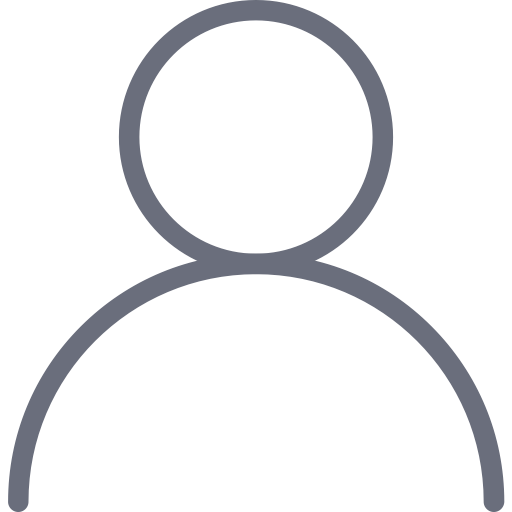 |
| マスダ ヒロミツ | |
| 理科教育講座 | |
| 教授 | |
Last Updated :2025/03/27
研究者基本情報
研究者
氏名
益田 裕充, マスダ ヒロミツ
基本情報
研究者氏名(日本語)
益田, 裕充研究者氏名(カナ)
マスダ, ヒロミツ
使用外国語
発表に使用する外国語
英語執筆に使用する外国語
英語
所属
学位
経歴
研究活動情報
研究分野
研究キーワード
論文
- 探究の過程の重点化に関する研究―導入で要因を抽出し課題を設定することが「見通し」と「振り返り」に与える影響に着目して―, 山内 宗治・益田 裕充・ 栗原 淳一・上原 永次・ 日暮 利明・大井 俊和, 2021年.3月, 群馬大学共同教育学部紀要 自然科学編, 第69巻, 27, 34
- 理科の実験計画を立案・記述する際のメタ認知的知識を獲得させる指導に関する研究, 栗原淳一・湯本裕貴・柏木純・益田裕充, 2021年.3月, 群馬大学共同教育学部紀要 自然科学編, 第69巻, 41, 50
- 問題解決の力を育成する理科授業に関する研究, 日暮利明・益田裕充, 2021年.3月, 群馬大学共同教育学部紀要 自然科学編, 第69巻, 61, 69
- 理科授業における探究の過程の重点化に関する研究-解決方法の立案に着目して-, 山内宗治・益田裕充・上原永次・日暮利明・倉林凌佑, 2021年.3月, 群馬大学教育実践研究, 第38号, 75, 82
- 理科授業における解決方法の立案に関する研究-自然事象の提示から予想・仮説の設定と検証計画の立案の局面の関係に着目して-, 益田裕充・山内宗治・鈴木駿・半田良廣, 2020年.3月, 群馬大学教育実践研究, 第37巻, 71, 78
- 小学校理科において実験計画を立案させる指導方法 -実験前後の測定の必要性を考えさせる効果-, 栗原淳一・青木利憲・栗原顯太・益田裕充, 2020年.3月, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 第68巻, 37, 43
- 探究の過程を踏まえた高校化学の授業プログラム開発に関する研究-バファリンAを教材とした成分分析を通して-, 亀田絵理・日置英彰・益田裕充, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 第68巻, 19, 26
- 大学生の理科授業を構想する能力に関する研究-理科授業デザインベース構造化シートを用いた課題の抽出, 益田裕充・半田良廣・田村敏之・藤本義博・栗原淳一, 2020年.3月, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 第68巻, 27, 35
- 思考力・判断力・表現力を育成する授業の構想に関する研究-理科授業デザインベース構造化シートを用いて, 斎藤剛志、益田裕充、半田良廣、安藤千尋、鈴木浩康, 2019年.3月, 群馬大学教育実践研究, 第36号, 47, 54
- 検証計画の立案に基づくカリキュラム・マネジメントに関する研究-反証例を扱う思考の枠組と計画シートの考案-, 益田裕充、斎藤剛志、藤本義博、半田良廣、神知己, 2019年.3月, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 第67巻, 39, 48
- 中学校理科教員の意識調査から明らかになった指導上の課題と改善の方向性, 鈴木浩康、藤本義博、益田裕充, 2019年.3月, 理科教育学研究, Vol.59, No.3, 401, 410
- 学習指導要領の目標に示された「考え方」としての「思考の枠組」の形成に関する研究-理科授業デザインベース構造化シートを用いた模擬授業と授業カンファレンスの往還を通して-, 益田裕充、栗原淳一、藤本義博、半田良廣、吉田和気, 2019年.3月, 臨床教科教育学会誌, 第18巻, 第2号, 47, 58, 研究論文(学術雑誌)
- 互生植物の葉の付き方の理解に関する研究, 半田良廣; 益田裕充; 下平有以; 藤本義博, 2018年08月, 科学教育研究, 42, 2, 140, 150, 研究論文(学術雑誌)
- 生態系における物質循環を理解する上で基礎となる小中学校理科の学習内容と問題点,群馬大学教育学部紀要自然科学編,第66巻,pp.49-56 査読有, 佐藤綾; 益田裕充, 2018年03月, 群馬大学教育学部紀要自然科学編, 66, 49, 56, 研究論文(学術雑誌)
- 理科指導法を通した学生の変容に基づく 教科専門科目の指導に関する考察, 益田 裕充; 杉山 奈津美; 日置 英彰; 佐藤 綾; 藤本 義博; 半田 良廣, 2018年, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 66, 29, 40, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 生態系における物質循環を理解する上で基礎となる 小中学校理科の学習内容と問題点, 佐藤 綾; 益田 裕充, 2018年, 群馬大学教育学部紀要 自然科学編, 66, 49, 57, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 教育実習の授業協議会から生起する共通の規範に関する考察, 益田 裕充; 藤本 義博; 小川 勇之助; 加瀬 健; 染谷 めぐみ, 2018年, 群馬大学教科教育学研究, 17, 1-8.
- 思考・判断・表現等を働かせるために欠かせない学習過程の構造ー「振り返って考える」ために必要な各過程の関係の構築ー, 益田 裕充, 2018年, 理科の教育, 67, 10, 13, 研究論文(学術雑誌)
- 主体的・対話的で深い学びを促進する教師の発話による働きかけに関する実証的研究-小学校第5学年「川の働き」の授業において-, 藤本義博; 佐藤友梨; 益田裕充; 小倉恭彦, 2017年11月, 理科教育学研究, 58, 2, 159, 173, 研究論文(学術雑誌)
- Attitude Survey Regarding Science and Academic Records of Elementary Teacher Trainees in Japan, Mutsumi Nakai; Minori Hashimoto; Kana Suematsu; Tomoya Nakai; Kohji,TerataHisashi Aoki; Hiromitsu Masuda; Norie Fujibayashi; Atsushi Muta; Hitoshi Nakai, 2017年, The Journal of East Asian Educational Research, The Journal of East Asian Educational Research, 4, 1, 87, 98, 研究論文(学術雑誌)
- 「化学」の授業におけるくすり教育プログラムの開発―アスピリン腸溶錠を教材として―, 日置 英彰; 青木 尚之; 小野 智信; 益田 裕充; 栗原 淳一, 2017年, 科学教育研究, 41, 1, 47, 53, 研究論文(学術雑誌)
- 物理基礎の授業における科学的な探究の能力の育成に関する事例的研究 : 自己調整を促す「金属の比熱測定実験」を事例として, 茂木 孝浩; 鈴木 悠一; 栗原 淳一; 益田 裕充, 2017年, 臨床教科教育学会誌, 17, 1, 95, 104, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 見方・考え方を働かせる授業で重要なことは何かー探究の過程の構造化によるコア仮説と思考力・判断力・表現力の育成ー, 益田 裕充, 2017年, 理科の教育, 66, 19, 22, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業を評価する能力の変容に関する研究 : 理科指導法と教育実習を経て形成される大学生の能力の検証, 益田 裕充; 藤本 義博; 半田 良廣; 関口 あかね, 2016年, 臨床教科教育学会誌, 16, 2, 105, 112, 研究論文(学術雑誌)
- 批判的思考プロセスによる教員養成課程学生の授業力形成に関する研究 : 「模擬授業の構想」から「新たな模擬授業案の提示」までの一連のカリキュラム編成を通して, 益田 裕充; 栗原 淳一; 半田 良廣; 櫻井 康之; 藤本 義博, 2016年, 臨床教科教育学会誌, 16, 2, 87, 94, 研究論文(学術雑誌)
- 天体の位置関係を作図によって位相角でとらえさせる指導が満ち欠けの現象を科学的に説明する能力の育成に与える効果, 栗原 淳一; 益田 裕充; 濤崎 智佳; 小林 辰至, 2016年, 理科教育学研究, 57, 1, 19, 34, 研究論文(学術雑誌)
- 理科を専門としない新任教師による理科授業の変容に関する研究 : 養成・導入期に身につける理科授業の資質・能力の検証, 益田 裕充; 半田 良廣; 藤本 義博; 田中 実穂, 2016年, 臨床教科教育学会誌, 16, 2, 95, 103, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業における「検証計画の立案」に関する研究 : 予想を検証する実験計画を立案する局面の反証可能性に着目して, 藤本 義博; 半田 良廣; 益田 裕充; 馬場 祐介, 2016年, 臨床教科教育学会誌, 16, 2, 67, 74, 研究論文(学術雑誌)
- 全国学力・学習状況調査(中学校理科)のメッセージを読むー科学的に探究する能力の基礎を育成する過程, 益田 裕充, 2016年, 理科の教育, 65, 17, 20, 研究論文(学術雑誌)
- 論理的推論に基づく仮説形成方略に関する研究 : 熟達者と新任者の対話的な教授行動を指標として, 益田 裕充; 半田 良廣; 本郷 友貴, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 2, 91, 98, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業を構想する能力の向上に関する研究 : メンターによるメタ認知能力獲得の支援を通して, 益田 裕充; 斉藤 剛志; 半田 良廣, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 2, 75, 82, 研究論文(学術雑誌)
- 認知論的アプローチと社会文化論的アプローチを融合させた理科授業に関する研究, 益田 裕充; 佐竹 彰弘, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 1, 83, 94, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業を活用したくすりに関する科学的リテラシーを向上させるカリキュラム開発 : 中学校理科第7単元「科学技術と人間」「自然と人間」に着目して, 日置 英彰; 山口 滉太; 益田 裕充; 半田 良廣; 松本 誠, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 1, 63, 73, 研究論文(学術雑誌)
- 新任教員の生活科における職能成長の研究 : PAC分析の比較から, 久保田 善彦; 刀川 啓一; 中谷 かおり; 野口 昌宏; 益田 裕充, 2015年, 宇都宮大学教育学部教育実践紀要, 1, 29, 34, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 理科授業を通して学び続ける教師の成長に関する研究 : メンターの発話を受け止めるプロテジェによる授業の変容を中心に, 益田 裕充; 半田 良廣; 今井 聖也, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 2, 83, 89, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業の構造化と「主体的な問題解決」を支えるメタ認知の育成に関する研究, 半田 良廣; 星野 沙織; 益田 裕充, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 2, 55, 63, 研究論文(学術雑誌)
- 学習モデルを転換させ理科授業力を向上させるプログラムに関する研究 : 探究の構造性を検討する学習モデルの構築を通して, 益田 裕充; 庄司 将人, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 1, 95, 103, 研究論文(学術雑誌)
- 子どもの批判的思考を促す教師の支援に関する研究, 益田 拓; 戸田 朱美; 益田 裕充, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 1, 75, 81, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業で自己調整能力を育成する教師の支援とその熟達に関する研究, 佐藤 友梨; 益田 裕充, 2015年, 臨床教科教育学会誌, 15, 1, 15, 22, 研究論文(学術雑誌)
- 子どもの認知発達を図る外的資源と熟達した教師の支援的介入に関する研究, 益田 裕充; 薄 京介; 益田 拓, 2014年, 臨床教科教育学会誌, 14, 2, 63, 71, 研究論文(学術雑誌)
- 机間指導中の教師のコーチングに関する研究-「自己の観察 結果に基づいた考察」を支援する熟達した教師のコーチングに着目して-, 益田 裕充; 戸田 朱美, 2014年, 臨床教科教育学会誌, 14, 2, 73, 80, 研究論文(学術雑誌)
- 子どもの科学的概念構築を促す教師の支援に関する研究 : ブリッシングアナロジー方略を用いた教授効果と「状況モデルに揺さぶりを起こす」橋渡し事例の有効性, 益田 裕充; 中島 一斗, 2014年, 臨床教科教育学会誌, 14, 2, 81, 89, 研究論文(学術雑誌)
- 理科授業を専門としない初任教師(採用一年次)の理科授業方略に関する研究 : IRF三項発話連鎖構造分析による熟達教師との比較を通して, 益田 裕充; 新井 正樹, 2013年, 臨床教科教育学会誌, 13, 2, 97, 104, 研究論文(学術雑誌)
- 学校経営の基本戦略に関する研究-学び合うミドルリーダーによる学校ビジョン分析を通して-, 益田 裕充, 2013年, 群馬大学教科教育学研究, 12, 17, 26, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 認知的葛藤を克服する対話的な授業における教授行動分析-肺胞の概念を構築する理科授業デザインを通して-, 益田 裕充; 酒井 尚美, 2013年, 臨床教科教育学会誌, 13, 1, 65, 72, 研究論文(学術雑誌)
- W型問題解決モデルを用いた科学的リテラシーの育成に関する研究 : 教師による子どもの科学的能力を形成する支援的な介入の実態, 益田 裕充; 楠 悠; 五島 政一, 2013年, 臨床教科教育学会誌, 13, 2, 105, 112, 研究論文(学術雑誌)
- 中学生の消化および呼吸の概念形成を支援する理科授業に関する実証的研究 : 機械的消化・化学的消化および肺胞で満たされている肺の概念に着目して, 江田 謙太郎; 益田 裕充; Eda Kentaro; Msuda Hiromitsu, 2013年, 群馬大学教育学部紀要. 自然科学編, 61, 79, 87
- 測定誤差の解釈を支援する理科授業デザイン-アクション・リサーチの視点を用いた体系的なアプローチ-, 益田 裕充; 田之上 大輔; 清水 秀夫, 2013年, 臨床教科教育学会誌, 13, 1, 73, 80, 研究論文(学術雑誌)
- 論理的推論に基づく仮説形成を図る教授方略に関する実証的研究, 益田 裕充; 柏木 純, 2013年, 理科教育学研究, 54, 1, 83, 92, 研究論文(学術雑誌)
- 概念化シートを用いたカテゴリー化による知の創造-蒸散に対する考え方の実態と変容, 益田裕充; 塩谷優奈, 2012年, 教材学研究, 第23巻, 研究論文(学術雑誌)
- 実験誤差を分析・解釈させ振り子の概念構築を図る理科授業に関する研究, 清水秀夫; 益田裕充, 2012年, 教材学研究, 第23巻, 研究論文(学術雑誌)
- IRF発話連鎖構造分析による理科授業のデザインベース研究 : 熟達した教師による「ものの重さと体積」の戦略的授業デザイン, 益田 裕充; 倉澤 友梨; 清水 秀夫, 2012年03月, 日本理科教育学会理科教育学研究, 52, 3, 131, 141
- 熟達者の理科授業参観が初任者の理科授業に与える影響, 益田裕充; 高橋愛夢, 2012年, 群馬大学教育学部紀要人文・社会科学編, 第61巻, 93, 102, 研究論文(学術雑誌)
- 理科・算数クロスカリキュラムが物の重さと体積の理解に及ぼす効果, 益田裕充; 倉澤友梨; 清水秀夫, 2012年, 群馬大学教科教育学研究, 第11号, 研究論文(学術雑誌)
- 教師のリボイシングによる支援的介入が理科授業に与える影響, 益田裕充; 松井裕太, 2012年, 理科教育学研究, Vol.53, No.2, 295, 303, 研究論文(学術雑誌)
- 科学的な概念の獲得を目指した理科授業のデザイン : 強い電磁石の条件を関連付けて考察させ,概念構築を図る授業デザイン, 清水 秀夫; 益田 裕充, 2012年, 臨床教科教育学会誌, 12, 2, 25, 32
- 小学生の電流回路作製時に現れる自己調整する能力と自己調整的な適応に関する研究, 益田裕充; 松原詩歩, 2012年, 理科教育学研究, Vol.53, No.1, 123, 132, 研究論文(学術雑誌)
- Little,J.W.の分析的枠組みを用いた授業力の専門的成長に関する実証的研究 : 教師集団による授業研究会の語りが教師個人の授業の学習に及ぼす影響, 益田 裕充; 淺野 貴之; 髙島 広平, 2012年, 臨床教科教育学会誌, 12, 2, 75, 82
- 理科授業を苦手とする小学校教師による授業方略の研究 : IRF三項連鎖構造を用いた考察の局面の検証を通して, 益田 裕充; 武 彩香, 2011年11月, 日本理科教育学会理科教育学研究, 52, 2, 105, 114
- 導入で一般法則を捉えさせることが,子どもの学びに与える影響, 増田 和明; 益田 裕充, 2011年, 臨床教科教育学会誌, 11, 2, 73, 80
- 解決可能な発達水準に到達するためのインタラクションの要素-星座の年周運動における協同的な学びの創造-, 益田裕充; 高橋愛夢, 2011年, 臨床教科教育学会誌, 第11巻, 第1号, 55, 61, 研究論文(学術雑誌)
- 角距離の概念と推論の相違が「月の満ち欠け」の理解に与える影響, 栗原 淳一; 益田 裕充, 2011年, 科学教育研究, Journal of Science Education in Japan, 35, 1, 47, 53
- 考察の局面におけるデジタルコンテンツ融合の一考察, 益田裕充; 武彩香; 強瀬雪乃, 2011年, 群馬大学教科教育学研究, 第10号, 15, 22, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 学びを動機づける理科授業の開発--事象提示により課題を捉えた子どもの検証過程の分析, 清水 秀夫; 益田 裕充, 2011年, 教材学研究, 22, 87, 94
- 教科書に掲載された動植物の教材史--小学校理科「花のつくりと結実」における植物教材の扱いを中心に, 益田 裕充; 川合 美奈, 2011年, 教材学研究, 22, 7, 14
- 影のでき方に着目した日食のモデル実験授業, 星野 友幸; 岡崎 彰; 益田 裕充; 丹羽孝良, 2011年03月, 群馬大学教育実践研究, Research in educational practice and development, Gunma University, 第28号, 28, 47, 55
- 受粉と結実をヘチマで学習することによる領域固有性と知的技能の実態, 益田裕充; 川合美奈, 2011年, 群馬大学教育実践研究, 第28号, 75, 82, 研究論文(学術雑誌)
- 教師による「言い換え」が授業の知識協同構成に与える影響 : Transacitive Discussionの質的分析カテゴリーを用いた理科授業分析に基づいて, 益田 裕充; 倉澤 友梨; 清水 秀夫, 2011年, 臨床教科教育学会誌, 11, 2, 65, 72
- 根拠を持って予想する活動が子どもの実感を伴った理解に与える影響-「ぐんま昆虫の森」における自然観察を通して-, 清水秀夫; 益田裕充, 2010年03月, 教材学研究, 21, 141, 148, 研究論文(学術雑誌)
- モデル実験による視点移動能力育成支援の試み--金星の見え方に関する授業を事例として, 吉野 晃生; 岡崎 彰; 益田 裕充; 丹羽 孝良, 2010年03月, 群馬大学教育実践研究, Research in educational practice and development, Gunma University, 27, 27, 47, 53
- 消化モデルを生成-評価-修正し科学的な概念に深化させる授業デザイン, 益田 裕充; 江田 謙太郎, 2010年, 臨床教科教育学会誌, 10, 2, 45, 51
- 演繹的に示した一般法則を活用する授業方略が科学的な思考力の深化に及ぼす影響, 淺野 貴之; 益田 裕充, 2010年, 臨床教科教育学会誌, 10, 1, 1, 7
- 教師による説明の公準の実態と授業経験による変容--「日の出前」「日の入り後」の扱いを中心に, 益田 裕充; 高橋 愛夢, 2010年, 臨床教科教育学会誌, 10, 1, 83, 90
- 小学校理科支援員に対する教師の評価と授業支援による子どもへの影響, 益田裕充, 2010年, 群馬大学教育学部研究紀要(自然科学編), 第58巻, 83, 92, 研究論文(学術雑誌)
- 小学校理科「溶解単元」における演繹的推論に基づく授業の効果-質量保存の概念形成に着目して-, 栗原淳一; 益田裕充, 2010年, 日本教材学会, Vol.21, 研究論文(学術雑誌)
- 小学校理科の実験結果を大学生はいかに考察するのか--養成教育の学生と教師の学習, 益田 裕充; 江田 謙太郎, 2009年, 群馬大学教科教育学研究, 第9号, 9, 11, 16
- 「教職実践演習」試行の報告と本実施に向けて, 齋藤周; 佐藤浩一; 山崎雄介; 江森英世; 益田裕充, 2010年, 群馬大学教育学部学校臨床総合センター紀要, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 理科授業を起点とした学校づくり : 子どもの学びを一貫して支援し実効性のある組織に, 益田 裕充, 2009年01月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 58, 1, 17, 19
- 実感を伴った理解を図る授業デザインに関する研究--第6学年理科「人と環境」の実践を通して, 清水 秀夫; 益田 裕充, 2009年, 臨床教科教育学会誌, 9, 2, 19, 27
- 演繹的推論による授業づくりに関する研究--小学校第3学年理科「磁石の性質」の学びに着目して, 増田 和明; 益田 裕充, 2009年, 臨床教科教育学会誌, 9, 2, 85, 92
- 理科授業における推論過程の分析とその背景となる教師の価値観の考察, 益田裕充, 2009年, 群馬大学臨床実践センター紀要, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 小学校理科授業者の育成をめぐる諸課題--教員養成系大学の大学生は小学校理科の学習内容をいかにとらえているか, 益田 裕充, 2008年, 群馬大学教科教育学研究, 第8号, 8, 61, 68
- 発展的な学習内容と推論の相違に基づく子どもの科学的認識の実態, 益田 裕充, 2009年07月10日, 理科教育学研究, Journal of research in science education, 50, 1, 67, 74
- 理科支援員の熟達・非熟達に関する事例的研究--理科支援員配置から10ヶ月を追って, 益田 裕充, 2009年, 臨床教科教育学会誌, 9, 1, 61, 66
- 生物の指標性を教材にした自然環境学習の展開, 益田 裕充, 2009年, 教材学研究, 20, 87, 94
- 「理科授業総合演習」における中学校理科(天文分野)の授業実践 (特集 教育学研究科「教科教育実践専攻」の新科目『○○科授業総合演習』の企画・実践・評価に関する総合的研究), 岡崎 彰; 益田 裕充; 奥沢 誠, 2008年, 群馬大学教科教育学研究, 8, 11, 20
- 中学生の科学的な概念の深化・拡大に関する研究, 益田裕充, 2008年, 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科博士論文, 学位論文(博士)
- 大規模地震に直面した中学生の実態と地震体験型学習の展開, 益田 裕充, 2008年, 教材学研究, 19, 179, 186
- 科学的知識の異なる小学校理科支援員の実験・観察時に見られるコミュニケーションの分析, 益田裕充, 2008年, 臨床教科教育学会, 第8巻, 第2号, 研究論文(学術雑誌)
- 教育行政が導く教育の情報化と理科教育, 益田裕充, 2007年, 理科の教育, Vol.56.No12, 665号
- 科学部生徒の探究活動に関する事例的研究, 益田裕充, 2007年, 科学教育研究, 31(4), 研究論文(学術雑誌)
- 学習内容の構造化を図る指導が学習者の概念の深化・拡大に及ぼす影響-化学変化と電気エネルギーをつなぐ自由電子の学びを通して-, 益田裕充, 2007年, 理科教育学研究, 48(2), 研究論文(学術雑誌)
- 子どもの直観からはじまる授業における教師の支援に関する研究, 益田裕充, 2007年, 臨床教科教育学会誌, 7(2), 研究論文(学術雑誌)
- 学習指導要領への位置づけの変遷と子どもの空間認識に基づく発展的な学習内容の検討 : 「月が満ち欠けする理由」をめぐって, 益田 裕充, 2007年, 科学教育研究, Journal of Science Education in Japan, 31, 1, 3, 10
- 葉脈の役割を比喩的に表現し合うコミュニケーション活動に基づくかかわり合い成り立ちの局面の検証, 益田裕充, 2007年, 臨床教科教育学会誌, 7(1), 79, 83, 研究論文(学術雑誌)
- 水流モデルから電流回路を類推する理科授業に関する研究 : ベースドメインの関係とターゲットドメインの関係を類推させるコミュニケーション活動を通して, 益田 裕充, 2006年11月30日, 理科教育学研究, Journal of research in science education, 47, 2, 41, 49
- 水蒸気概念の形成を図る教材と指導法の研究--中学校理科「天気とその変化」に着目して, 益田 裕充, 2006年, 教材学研究, 17, 135, 138
- 小学校理科地学領域における発展的な学習内容 : C領域に掲載された教科書の記述調査から, 益田 裕充, 2006年05月25日, 地学教育, 59, 3, 109, 114
- 協同的な学びの成立に寄与する発展的な学習内容が子どもの科学的概念の形成に及ぼす影響, 益田 裕充, 2005年09月, 理科教育学研究, 46, 1, 91, 99, 研究論文(学術雑誌)
- 授業の芯をいかに創るか, 益田裕充, 2005年, 理科の教育, Vol54No8, 637号
- 中学生の「分解者による分解」概念形成の実態と, 土の理解がその形成に与える影響, 益田 裕充, 2005年, 科学教育研究, Journal of Science Education in Japan, 29, 4, 283, 293
- 認知的葛藤を促す教材に関する研究 イカの軟骨とセキツイの理解, 益田 修; 益田 裕充, 2005年, 教材学研究, 16, 133, 136
- 発展的な学習内容と教材に関する研究 理科授業において扱う進化の内容と教材を事例として, 益田 裕充, 2005年, 教材学研究, 16, 129, 132
- 学びの目標を感得できる教材のあり方についての研究--小中学校における理科教材のつながりを事例として, 益田 裕充, 2004年, 教材学研究, 15, 221, 224
- 学習内容の厳選と指導法の相違が中学生の火成岩概念の形成に与える影響, 益田 裕充, 2004年05月25日, 地学教育, 57, 3, 59, 67
- 教師の記憶が中学生の記憶に与える影響とその記憶要素の実態, 益田 裕充, 2004年, 科学教育研究, Journal of Science Education in Japan, 28, 2, 83, 93
- 理科教師の責任 : 発展的な学習の時間で「・・・程度にとどめる」の突破を, 益田 裕充, 2003年05月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 52, 5, 22, 24
- 子どもの学びをコーディネートし学びの文脈を評価する, 益田 裕充, 2001年12月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 50, 12, 29, 31
- 科学的知識構成の指標としてのメタファー研究 : 学びのはじまりにおける子どもたちの非科学的な表現が意味すること, 益田 裕充, 2000年12月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 49, 12, 26, 28
- 子どものコミュニケーション活動に見るメタファーとしての化学概念理解の深まり : 中学生の分解概念理解を事例として, 益田 裕充; 森本 信也, 2000年11月30日, 理科教育学研究, Journal of research in science education, 41, 2, 21, 30
- 自己効力感から始まる理科授業 -学びを見直す「学びの構造図」作りと協同的学習-, 益田 裕充, 1998年07月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 47, 7, 472, 475
- 認知的方略の育成をめざす理科学習の在り方 Messing About論に基づく学びの構想, 益田 裕充, 1997年12月15日, 理科の教育 = Science education monthly, 46, 12, 808, 811
- 大学生の理科授業を構想する能力に関する研究 -理科授業デザインベース構造化シートを用いた課題の抽出-, 益田裕充; 半田良廣; 田村敏之; 藤本義博; 栗原淳一, 2020年03月, 群馬大学教育学部紀要自然科学編, 68, 27, 35, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 小学校理科において実験計画を立案させる指導方法 -実験前後の測定の必要性を考えさせる効果-, 栗原淳一; 青木利憲; 栗原頌太; 益田裕充, 2020年03月, 群馬大学教育学部紀要自然科学編, 68, 37, 43
- 学習指導要領の目標に示された「考え方」としての「思考の枠組」の形成に関する研究-理科授業デザインベース構造化シートを用いた模擬授業と授業カンファレンスの往還を通して-, 益田裕充; 栗原淳一; 藤本義博; 半田良廣; 吉田和気, 2019年03月, 臨床教科教育学会誌, 第18巻, 第2号
- 演繹的推論に基づく課題解決学習が質量保存の科学的な概念の形成に与える影響, 栗原淳一; 益田裕充, 2010年03月, 教材学研究, 第21巻, 49, 56
MISC
- 蒸散概念の実態とその変容に関する研究 : 概念化シートを教材として用いたカテゴリー化を通して, 益田 裕充; 塩谷 優奈, 2012年, 教材学研究, 23, 127, 136
- 1L-01 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究1 : IRF発話連鎖構造分析を用いた熟達した教師による課題・予想のデザイン(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 倉沢 友梨; 益田 裕充; 清水 秀夫, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 244, 244
- 1L-02 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究2 : IRF発話連鎖構造分析を用いた理科授業が苦手な小学校教師による考察のデザイン(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 武 彩香; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 245, 245
- 1L-03 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究3 : 自己調整学習におけるCOPESを指標とした電流回路作製時に出現する自己調整的な適応(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 松原 詩歩; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 246, 246
- 1L-04 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究4 : 授業研究会による教師の学習をLittle, J.W.の分析的枠組みから検証する(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 高島 広平; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 247, 247
- 1L-05 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究5 : 実験操作の過程で条件の精緻な制御を試行する子どもの学び(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 川崎 祐子; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 248, 248
- 1L-06 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究6 : 協調的な学習を意図する教師と教室に現れた子どもの学び(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 塩谷 優奈; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 249, 249
- 1L-07 学習科学を志向する理科授業のデザインベース研究7 : 小学生に誤差を分析・解釈させ概念構築を図る振り子の授業デザイン(授業研究,学習指導,一般研究発表(口頭発表)), 清水 秀夫; 益田 裕充, 2011年, 日本理科教育学会全国大会要項, 61, 250, 250
- 1F-01 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討1 : 理科授業研究の検証「授業の反省」を教師はいかに評価するのか(一般研究発表(口頭発表)), 高島 広平; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 175, 175
- 1F-02 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討2 : 自己効力感を育む学びの動機づけとしての課題設定場面の構造化(一般研究発表(口頭発表)), 清水 秀夫; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 176, 176
- 1F-03 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討3 : 子どもは電流回路を作製する過程でいかに自己調整するのか(一般研究発表(口頭発表)), 松原 詩歩; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 177, 177
- 1F-04 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討4 : 自律的な学びの創造とナイン・チェックリストを用いた知の分析(一般研究発表(口頭発表)), 川崎 祐子; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 178, 178
- 1F-05 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討5 : 科学概念形成に至るプロセスと学びのストーリー性に関する効果(一般研究発表(口頭発表)), 栗原 淳一; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 179, 179
- 1F-06 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討6 : モデル化のサイクルを用いた知の多様な表現と科学概念構築(一般研究発表(口頭発表)), 江田 謙太郎; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 180, 180
- 1F-07 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討7 : 「物と重さ」の理解に算数・理科クロスカリキュラムがもたらす効果(一般研究発表(口頭発表)), 倉沢 友梨; 益田 裕充; 清水 秀夫, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 181, 181
- 1F-08 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討8 : 概念化シートを用いたカテゴリー化による知の表現(一般研究発表(口頭発表)), 塩谷 優奈; 益田 裕充; 高橋 学, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 182, 182
- 1F-09 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討9 : 観察・実験の読解に寄与するディジタルコンテンツ融合の視点(一般研究発表(口頭発表)), 武 彩香; 益田 裕充; 強瀬 雪乃, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 183, 183
- 1F-10 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討10 : 手段-目標分析による下位目標の抽出と問題解決に要する「間」の分析(一般研究発表(口頭発表)), 高橋 愛夢; 益田 裕充; 丹羽 孝良, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 184, 184
- 2J-09 地球温暖化実験装置の改善及び,その装置を用いた授業実践(一般研究発表(口頭発表)), 芹澤 嘉彦; 奥沢 誠; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 368, 368
- 2L-07 安価な簡易霧箱を用いた,「放射線」授業実践の報告(一般研究発表(口頭発表)), 小柏 洋輔; 奥沢 誠; 益田 裕充, 2010年, 日本理科教育学会全国大会要項, 60, 376, 376
- デジタルコンテンツを融合させた理科授業の検証, 益田 裕充; 武 彩香; 強瀬 雪乃, 2010年, 群馬大学教科教育学研究, 10, 15, 22
- 1C-07 演繹的推論に基づく理科授業の創造(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 112, 112
- 1C-08 演繹的推論に基づく理科授業の創造 : 小学校第5学年「物の溶け方」の学びに着目して(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 栗原 淳一; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 113, 113
- 1C-09 演繹的推論に基づく理科授業の創造 : 小学校第6学年「電流の生み出す力」の学びに着目して(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 淺野 貴之; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 114, 114
- 1C-10 演繹的推論に基づく理科授業の創造 : 小学校第3学年「磁石の性質」の学びに着目して(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 増田 和明; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 115, 115
- 1F-03 実感を伴った理解を図るための学びに関する研究(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 清水 秀夫; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 144, 144
- 1N-10 一人ひとり作製・観察できる安価で簡単な霧箱の開発と,その教材としての評価(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第59回全国大会), 小柏 洋輔; 奥沢 誠; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 247, 247
- P-22 モデル実験による視点移動能力の支援の試み : 金星の見え方に関する授業を事例として(ポスター発表,日本理科教育学会第59回全国大会), 吉野 晃生; 岡崎 彰; 益田 裕充; 丹羽 孝良, 2009年, 日本理科教育学会全国大会要項, 59, 362, 362
- B1-03 科学的な概念を深化・拡大する「消化・吸収」の授業デザイン : 子どもの学びの実態から授業の構想まで(セッションB1,日本理科教育学会第48回関東支部大会), 江田 謙太郎; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会関東支部大会研究発表要旨集, 48, 30, 30
- B1-04 星座の年周運動の授業デザインに関する考察 : 子どもの理解の実態に根ざした授業創造の視点から(セッションB1,日本理科教育学会第48回関東支部大会), 高橋 愛夢; 益田 裕充; 丹羽 孝良, 2009年, 日本理科教育学会関東支部大会研究発表要旨集, 48, 31, 31
- D1-02 小学校植物領域における日常生活との関連を図る知的技能の実態(セッションD1,日本理科教育学会第48回関東支部大会), 川合 美奈; 益田 裕充, 2009年, 日本理科教育学会関東支部大会研究発表要旨集, 48, 60, 60
- 1F-03 小学校理科支援員の配置効果に関する研究(一般研究発表(口頭発表),日本理科教育学会第58回全国大会), 益田 裕充, 2008年, 日本理科教育学会全国大会要項, 58, 185, 185
- 2H-11 協同的な学びの成立に寄与する発展的な学習内容が子どもの科学的概念の形成に及ぼす影響(授業研究・学習指導, 日本理科教育学会第54回全国大会), 益田 裕充, 2004年, 日本理科教育学会全国大会要項, 54, 320, 320
- 2L課04-3 子どものコミュニケーション活動に見るメタファーとしての科学概念理解の深まり, 益田 裕充, 1999年, 日本理科教育学会全国大会要項, 49, 273, 275
- 2D課01 協同的な学びを支援する理科授業, 益田 裕充, 1998年, 日本理科教育学会全国大会要項, 48, 222, 223
- 科学概念形成とその阻害要因に関する研究 : クリティカル・バリヤー克服の授業方略を中心に, 益田 裕充, 1996年03月, 理科教育研究誌, 8, 61, 70
- C2-09 生物のつながりにおける分解概念の定着に関する研究 : 有機物の「分解」概念の実態とクリティカル・バリヤーの存在, 益田 裕充; 戸北 凱惟, 1995年, 日本理科教育学会全国大会要項, 45, 187, 187
- B-209 地域微環境調査に基づく環境教育, 益田 裕充, 1993年, 日本理科教育学会全国大会要項, 43, 98, 98
書籍等出版物
- 中学校教育課程実践講座 理科, 共著, 小林辰至・益田裕充ほか, 2017年, 259, 8
- 理科の教育 子どもの目が輝く考察とは(理論編), 単著, 益田裕充, 日本理科教育学会, 2021年.3月, 4, 4, 学術書
- 確かな学力を育む理科教育の責任-「わかる」授業の構想から実践まで-, 2003年
- CD-ROM版中学校理科教育実践講座ACIES第5巻, ニチブン, 2003年
- 学校ビオトープQ&A, 2001年
- カラーブック理科資料埼玉県版(改訂版), 東京法令出版, 2001年
- 理科から発信する総合的学習の学力, 明治図書, 2001年
- 中学校理科の絶対評価規準づくり, 明治図書, 2002年
- 論理を構築する子どもと理科授業, 2002年
- 個に応じた指導に関する指導資料-発展的な学習や補充的な学習の推進-(中学校理科編), 教育出版株式会社, 2002年
- 平成13年度小中学校教育課程実施状況調査報告書, 2003年
- 子どもの感性がつくる理科授業, 東洋館出版社, 2003年
- 研究授業中学校理科, 明治図書, 2004年
- 確かな学力を育てる中学校理科授業, 東洋館出版社, 2004年
- 中学校新授業への挑戦4理科指導と評価一体化の実際, 明治図書, 2005年
- みんなと学ぶ小学校理科教師用指導書研究編, 学校図書, 2005年
- 楽しい理科授業, 明治図書, 1999年
- 楽しい理科授業, 明治図書, 1999年
- 楽しい理科授業, 明治図書, 1999年
- 楽しい理科授業, 明治図書, 2004年
- 楽しい理科授業, 2008年
- 新版 小学校理科指導の研究, 建帛社, 2009年
- 中学校新学習指導要領の展開 理科編, 明治図書出版, 2008年
- 楽しい理科授業, 2008年
- 親子で楽しむ埼玉の自然たんけん, 日本標準, 1997年
- SCIRE・中学校理科教育実践講座, ニチブン, 1996年
- 環境教育実践事例集, 第一法規出版, 1995年
- 楽しい理科授業, 明治図書, 2009年
- RISEいんぐ, 学校教育研究所, 2010年
- 教科研究理科, 学校図書, 2010年
- 教育時評, 財団法人学校教育研究所, 2011年
- 教科教育-群馬大学からの発信-, 群馬大学教科教育研究会編, 2011年
- 理科授業の理論と実践-子どもの「すごい!」を引き出す手作り授業-, 関東学院大学出版, 2011年
- 新しい教科書と授業改善, 学校図書, 2012年
- 学校力のアップとカリキュラムマネジメント, 学校図書, 2013年
- 熟達した教師が創る最新理科授業中学校1年, 学校図書, 2012年
- 熟達した教師が創る最新理科授業中学校2年, 学校図書, 2012年
- 熟達した教師が創る最新理科授業中学校3年, 学校図書, 2012年
- 理科指導法の研究-大学生はなぜ4本足のニワトリを描くのか-, 上毛新聞社, 2012年
- 平成22年度教員養成FDセンター推進プロジェクト報告書, 2011年
- 平成23年度教員養成FDセンター推進プロジェクト報告書, 2012年
- 理科の教育, 2013年
- 知性を高め未来を創る理科授業, 上毛新聞社, 2019年04月
講演・口頭発表等
- 探究の過程の重点化に関する研究, 山内宗治・益田裕充・栗原淳一・上原栄次・日暮利明・大井俊和, 日本理科教育学会関東支部大会, 2020年
- 理科授業における探究の過程の重点化に関する研究, 山内宗治・益田裕充・上原栄次・日暮利明・倉林凌佑, 日本理科教育学会関東支部大会, 2020年
- 授業研究を発展させるための授業研究組織の設計と実践, 藤本義博・岡本弥彦・益田裕充・木原俊行・柴田好章, 日本理科教育学会第70回全国大会, 2020年
- 資質・能力を育成する構造化シートの開発に関する研究, 山内宗治・益田裕充・上原栄次・日暮利明・安藤千尋, 日本理科教育学会第70回全国大会, 2020年
- 類推に基づく解決方法の立案に関する研究, 上原栄次・益田裕充・日暮利明・山内宗治・尾池早紀, 日本理科教育学会第70回全国大会, 2020年
- コア仮説に基づく理科授業力の形成に関する研究, 益田裕充・上原栄次・山内宗治・日暮利明・斎藤夏樹, 日本理科教育学会第70回全国大会, 2020年
- 理科支援員が参加した授業が子どもに与える影響-観察・実験時におけるコミュニケーション分析等を通して-, 日本理科教育学会第47回関東支部大会, 2008年
- 演繹的推論に基づく理科授業の創造, 日本理科教育学会第59回全国大会, 2009年
- 演繹的推論に基づく理科授業の創造-小学校第5学年「物の溶け方」の学びに着目して-, 日本理科教育学会第59回全国大会, 2009年
- 演繹的推論に基づく理科授業の創造-小学校第6学年「電流の生み出す力」の学びに着目して-, 日本理科教育学会第59回全国大会, 2009年
- 演繹的推論に基づく理科授業の創造-小学校第3学年「磁石の性質」の学びに着目して-, 日本理科教育学会第59回全国大会, 2009年
- 小学校理科支援員の配置効果に関する研究, 日本理科教育学会第58回全国大会, 2008年
- 一人ひとり作製・観察できる安価で簡単な霧箱の開発とその教材としての評価, 日本理科教育学会, 2009年
- モデル実験による視点移動能力の支援の試み-金星の見え方に関する授業を事例として-, 日本理科教育学会, 2009年
- 科学的な概念を深化・拡大する消化吸収の理科授業デザイン-子どもの学びの実態から授業の構想まで-, 日本理科教育学会関東支部大会, 2009年
- 星座の年周運動の授業デザインに関する考察-子どもの理解の実態に根ざした授業創造の視点から-, 日本理科教育学会関東支部大会, 2009年
- 小学校植物領域における日常生活との関連を図る知的技能の実態, 日本理科教育学会関東支部大会, 2009年
- 理科における教材づくりに求められるもの-1枚の葉が語る世界-, 日本理科教育学会全国大会, 2002年
- 協同的な学びの成立に寄与する発展的な学習内容が子どもの科学的概念の形成に及ぼす影響, 日本理科教育学会全国大会, 2004年
- 発展的な学習と教材の位置づけに関する研究, 日本教材学会全国大会, 2004年
- 理科教育における質的研究の展望と課題-子どものコミュニケーション活動に見るメタファーとしての科学概念理解の深まり-, 日本理科教育学会第49回全国大会, 1999年
- Messing About論に基づく学びの構想-Concept Mapによる概念の分析を通して-, 日本理科教育学会関東支部大会, 1998年
- 科学概念形成とその阻害要因に関する研究Ⅲ-素朴概念の比喩的な側面を支援する理科授業-, 日本理科教育学会関東支部大会, 1998年
- 認知論的アプローチによる理科授業の研究-協同的な学びを支援する理科授業-, 日本理科教育学会第48回全国大会, 1998年
- 科学概念形成とその阻害要因に関する研究Ⅱ-状況的な認知を構成する既有知識がメタファーに及ぼす影響-, 日本理科教育学会関東支部大会, 1997年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討3―子どもは電流回路を作製する過程でいかに自己調整するのか, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討6-モデル化のサイクルを用いた知の多様な表現と科学概念構築-, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討1-理科授業研究の検証「授業の反省」を教師はいかに評価するのか-」, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討2-自己効力感を育む学びの動機づけとしての課題設定場面の構造化-, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討5―科学概念形成に至るプロセスと学びのストーリー性に関する効果, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討7-「物と重さ」の理解に算数・理科クロスカリキュラムがもたらす効果-, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討8―概念化シートを用いたカテゴリー化による知の表現, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討9-観察・実験の読解に寄与するディジタルコンテンツ融合の視点-, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討4―自律的な学びの創造とナイン・チェックリストを用いた知の分析, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 子どもの科学概念形成を志向する理科授業方略の実践的検討10-手段-目標分析による下位目標の抽出と問題解決に要する「間」の分析-, 日本理科教育学会第60回全国大会, 2010年
- 教師が設計する授業デザインに関する研究2, 日本理科教育学会全国大会, 2013年
- 学習科学を志向する理科授業デザインベース研究5‐実験操作の過程で条件の精緻な制御を試行する子どもの学び‐, 日本理科教育学会全国大会, 2011年
- 学習科学を志向する理科授業デザインベース研究6‐協調的な学習を意図する教師と教室に現れた子どもの学び‐, 日本理科教育学会, 2011年
- 学習科学を志向する理科授業デザインベース研究7‐小学生に誤差を分析・解釈させ概念構築を図る授業デザイン‐, 日本理科教育学会全国大会, 2011年
- 科学的概念の獲得を目指した理科授業のデザイン‐強い電磁石の条件を関連付けて考察させ,概念構築を図る授業デザイン‐, 日本理科教育学会第50回関東支部大会, 2011年
- 熟達者の理科授業参観が初任者の理科授業に与える影響, 日本理科教育学会第50回関東支部大会, 2011年
- IRF発話連鎖構造分析を用いた教師の自律性支援に関する研究, 日本理科教育学会第50回関東支部大会, 2011年
- 英国・米国の学習内容を組み込んだ授業が消化・吸収の概念形成に及ぼす影響‐機械的消化・化学的消化および肺胞で満たされている肺の概念に着目して, 日本理科教育学会第62回全国大会, 2012年
- 認知的葛藤に解決に「教師のリボイシングによる支援的介入」が果たす役割, 日本理科教育学会第62回全国大会, 2012年
- 論理的推論に基づく仮説形成を図る教授方略に関する実証的研究, 日本理科教育学会第62回全国大会, 2012年
- 今日的課題を踏まえた授業実践をいかに研究につなぐか-実践的研究の課題と方法-, 日本学校教育学会, 2012年
- 理科を専門としない初任教師と熟達教師の授業の相違に関する研究―IRF発話連鎖構造分析,リボイシング分析の観点から-, 日本理科教育学会第51回関東支部大会, 2012年
- 理科授業で認知的葛藤を生起させるパネルディスカッション法に関する研究, 日本理科教育学会第51回関東支部大会, 2012年
- W型問題解決モデルを用いた科学的リテラシーの育成に関する研究-昆虫の口の形からはじまる科学的な思考過程の追究-, 日本理科教育学会第51回関東支部大会, 2012年
- 論理的推論に基づくアブダクションに関する研究, 日本理科教育学会第50回関東支部大会, 2011年
- 足場づくりと子どもの思考スタイルに関する事例的検証, 臨床教科教育学会, 2011年
- 子どもによる協同的な学習が与える効果の検証-中学校3年「星座の年周運動」の学習から-, 臨床教科教育学会, 2011年
- 学習科学を志向する理科授業デザインベース研究1‐IRF発話連鎖構造分析を用いた熟達した教師による課題・予想のデザイン‐, 日本理科教育学会全国大会, 2011年
- 学習科学を志向する理科授業デザインベース研究2‐IRF発話連鎖構造分析を用いた理科授業が苦手な小学校教師による考察のデザイン‐, 理科教育学会全国大会, 2011年
- 「学習科学を志向する理科授業デザインベース研究3‐自己調整学習におけるCOPESを指標とした電流回路作製時に出現する自己調整的な適応‐, 日本理科教育学会全国大会, 2011年
- 「学習科学を志向する理科授業デザインベース研究4‐授業研究会による教師の学習をLiitle,J.W.の分析的枠組みから検証する‐, 日本理科教育学会全国大会, 2011年
- 中学生の「人体」に関する認識の実態, 日本理科教育学会第50回関東支部大会, 2011年
- 測定誤差の解釈を支援する理科授業デザイン, 日本理科教育学会第51回関東支部大会, 2012年
- 中学生が素朴概念を転換して肺胞の概念をとらえる認知過程, 日本理科教育学会第51回関東支部大会, 2012年
- 教師が設計する授業デザインに関する研究1, 日本理科教育学会全国大会, 2013年
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 協働学習支援ツールによる活用型授業とブレンディッドラーニングによる教員研修の開発, 益田 裕充, 科学研究費, 2016年04月, 2019年03月, 研究代表者, 競争的資金
- メタ認知的活動の促進による科学的能力の育成に関する研究, 栗原 淳一; 益田 裕充; 山田 貴之, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 群馬大学, 2018年04月01日, 2021年03月31日, 本研究は、理科授業において批判的思考のプロセスを組み込んでメタ認知的活動を促し、「科学的探究を評価して計画する能力」を育成する指導方法の開発とその効果を検証するものである。 2019年度は、2018年度に開発した指導方法を学校現場での基礎的な実践から、修正点を見いだし、改善した。まず、2018年度に定義した「検証計画を立案する能力」の下位能力(要素)の再検討を行い、下位能力を「条件の整理」、「具体的な操作・手順」、「現象との対応(モデル化)」、「結果の見通し」の四つに修正した。この四つについて生徒が記述・立案できる指導プログラムを中学校において二つ実践した。どちらの実践も、指導のポイントは、四つの要素を記述する必要性をとらえさせ、自らの検証計画(実験計画)を評価・修正させることとした。その手法は、現状の生徒の実験計画の記述を基に四つの要素を記述する必要性をとらえさせるもの、実験計画の記述モデル(実験計画立案用ビジュアルルーブリック)を生徒に提示してその解釈をさせることで四つの要素を記述する必要性をとらえさせるものの二つとした。この二つの実践から、生徒は批判的思考のプロセスをたどり、その中でメタ認知的活動を行い、高い基準の実験計画を立案することができたことが明らかとなった。この成果を、2019年度第7回日本科学教育学会研究会で発表した。 また、小学校において主実験を行い実験前後の測定の必要性をとらえさせる指導実践事例を分析し、その効果を明らかにした。, 競争的資金, 18K02655
- 科学的な見方や考え方に基づくくすり教育プログラムの開発に関する実証的研究, Empirical Research for enhancement of medication literacy based on the scientific view and thinking, 益田 裕充; 日置 英彰; 栗原 淳一, MASUDA Hiromitsu, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究, Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 挑戦的萌芽研究, Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 群馬大学, Gunma University, 2015年04月01日, 2018年03月31日, 研究代表者, 本研究は科学的な見方や考え方に基づく、くすりのリテラシーを向上させるプログラムの開発を目的とした。まず、中学校理科「科学技術と人間」等で他の学習内容との関連を図りながらくすり教育プログラムを開発した。くすりの開発と自然破壊、恩恵の享受と配分等を扱い座薬や腸溶剤を教材とした実験を通し、中学生が、薬に潜む科学技術等について理解することで、科学的リテラシーの形成を実証することができた。次に、高等学校化学の取扱を中核にしてプログラムを開発した。実際のくすりを使用した実験を通して、代謝や吸収についての学習内容と密接に関連させたプログラムを開発した。本研究で得られた結果を論文にまとめ学会等で発表し広めた。, This research project was designed to enhance medication literacy based on the scientific view and thinking. Medicinal science is relevant to many learning contents in junior and high school science class. Accordingly, we developed a learning program for medicinal education in science class utilizing suppositories and enteric-coated tablets as an experimental material. The mechanism for the main action, side effects and the reducing side effects is closely related to the content of science courses, such as neutralization, melting, solubility, absorbability, metabolism and so on. Classwork was performed based on the program. Comparison of pre- and post-questionnaires for students and analysis of their worksheets revealed that students gained not only medication literacy but also science literacy through the program., 競争的資金, 15K12368
- 理科授業を通して学び続ける教師教育プログラムの開発に関する実証的研究, 理科授業を通して学び続ける教師教育プログラムの開発に関する実証的研究, 益田裕充, 科学研究費補助金, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2013年, 2016年, 研究代表者, 競争的資金
- IRF発話連鎖構造分析を言語活動の評価に用いた教師の授業力形成に関する実証的研究, IRF発話連鎖構造分析を言語活動の評価に用いた教師の授業力形成に関する実証的研究, 益田裕充, 科学研究費補助金, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2012年, 2013年, 研究代表者, 競争的資金
- 子どもの科学的リテラシーを育成する教育システムの開発に関する実証的研究, 子どもの科学的リテラシーを育成する教育システムの開発に関する実証的研究, 科学研究費補助金, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2011年, 2014年, 競争的資金
- 教えて考えさせる理科授業の創造-演繹的推論に基づく習得型理科授業の創造-, 教えて考えさせる理科授業の創造-演繹的推論に基づく習得型理科授業の創造-, 益田裕充, 科学研究費補助金, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2009年, 2011年, 研究代表者, 競争的資金
- デジタルコンテンツとモデル実験とを有機的に結び付けた天文学習プログラムの開発, 科学研究費補助金, 2011年, 2012年, 競争的資金
- デジタルコンテンツとモデル実験とを有機的に結び付けた天文学習プログラムの開発, Grant-in-Aid for Scientific Research, 2011年, 2012年, 競争的資金
- 科学的な探究の特徴から理科授業を省察する教師教育プログラムの開発に関する研究, 益田 裕充; 加藤 圭司; 藤本 義博; 片平 克弘; 久保田 善彦; 栗原 淳一; 上原 永次, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 基盤研究(B), 群馬大学, 2019年04月01日, 2024年03月31日, 本年度の研究実績は論文(査読付)5報、学会発表(国内、全国大会)4報となる。特に、研究代表者が発表した「大学生の理科授業を構想する能力に関する研究-理科授業デザインベース構造化シートを用いた課題の抽出-」と「理科授業における解決方法の立案に関する研究-自然事象の提示から予想・仮説の設定と検証計画の立案の局面の関係に着目して-」は、研究の柱となる「理科授業における探究の過程」や「養成教育」「教師の熟達」に求められる能力の育成にとって重要な研究の骨格となる論文として示すことができた。代表者および分担者は、これまで学生を対象としたプログラムとして、模擬授業から授業カンファレンス・授業リフレクションをサイクル化するプログラムの有効性を実証してきている。これを構造化シートとして汎用性の高いものへと発展させる研究の成果を示すことができたのである。さらに、研究分担者の発表論文として「探究の過程」や「実験計画の立案」といった理科授業のデザインベースとなる研究の知見を示すことができた。学会発表では日本理科教育学会全国大会を中心に成果の一部を公開することができた。 本研究の核心をなす学術的な「問い」は,DBRの概念を援用し新学習指導要領理科で示された科学的な探究の過程に着目し,この成立の条件とその授業で培われる子どもの資質・能力の評価を切り離さず研究者の介入による効果的な協議手法を検討しながら,実際の理科授業を教師同士に協議させ,学び続ける教師教育プログラムを開発することにある。こうした点で、研究初年度に研究代表者が研究の成果として今後の研究推進の中核となる論文をまとめ、その成果を示すことができたのである。, 19H01663
- 授業研究を発展させるための授業研究ポータルサイトの設計と運用研究, Design and operation study of a lesson study portal site for developing lesson study, 藤本 義博; 岡本 弥彦; 木原 俊行; 柴田 好章; 益田 裕充; 藤枝 秀樹; 野内 頼一; 後藤 文博; 小倉 恭彦; 遠山 一郎, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 基盤研究(B), Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 岡山理科大学, Okayama University of Science, 2019年04月01日, 2022年03月31日, 本研究は,平成29年文部科学省告示の学習指導要領が目指す主体的・対話的で深い学びの実現による資質・能力の育成や国内外の学力調査の結果から明らかになった課題を解決する授業研究を発展させるために,「コラボレーションツールを活用した授業研究ポータルサイト」の設計と運用のあり方を明らかにすることである。研究1年目の2019年には,まず11月にGoogleのclassroomを活用した授業研究ポータルサイト「チーム理科」を構築し,中学校の理科教員を目指す岡山理科大学4年生10名に対して,観察・実験を行う授業の指導案と板書計画等の授業研究の指導を行った。この試行により,Googleのclassroomの利用について一定の成果を得たが,アカウント作成がgmailに依存するため,日頃gmailを利用しない学生にとってプッシュ通知を見逃すという課題が残った。そこで,2020年1月には,利用するメールに依存しないコラボレーションツールSLACKを利用して「授業研究リレー2020」を構築し,研究協力校の中学校と高等学校の理科教員16名に対して試行を開始した。具体的には,授業研究発展要因のうち「①分散型リーダーシップの発揮」を設計に位置づけて,同一の指導案ごとにチャンネル(グループ)をつくり,チャンネル(グループ)ごとにリーダーを置くことで,互いの課題を共有して授業研究をリレーして推進することとした。この「授業研究リレー2020」を日常的に利用して,指導案等の検討をオンラインで行い,2020年2月18日には竹富町立大原中学校,19日には竹富町立波照間小中学校,20日には石垣市立石垣中学校で同一の指導案による授業研究リレーを行い,授業研究推進の成果が得られた。本研究1年目の研究成果は,2020年2月29日の日本教育工学会全国大会で新型コロナウイルスのためオンラインによる研究成果の発表を行った。, 19H01726
- 協働学習支援ツールによる活用型授業とブレンディッドラーニングによる教員研修の開発, Development of teacher training by utilizing typed class with collaborative learning support tool and blended learning, 藤本 義博; 益田 裕充; 荒尾 真一; 稲田 佳彦; 宮地 功; 鈴木 康浩; 小倉 恭彦; 尾島 正敏; 波平 長真; 鈴木 康浩; 佐藤 友梨; 吉武 美岐; 神 孝幸, FUJIMOTO Yoshihiro; OGURA Yasuhiko; OJIMA Masatoshi; NAMIHIRA Nagamasa; SUZUKI Yasuhiro; SATO Yori; YOSHITAKE Miki; JIN Takayuki, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 基盤研究(B), Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 2015年04月01日, 2019年03月31日, 協働学習を促進するために、分担して観察した結果やそれを根拠にした考えをタブレット端末に表示して比較できるようにした。その結果、新たな考えの形成を促進した。また、「他の人に自分の考えを伝えたいと思う」、「他の人と話し合うと、自分では気づかなかったことに気づく」という意識の平均値が上昇し、有意差が認められた。 ブレンディッドラーニングによる教員研修で、模範の授業事例の指導案と授業の様子を映像で示して、授業研究を進めた。その結果、それぞれの学校の実態や指導する教員のパーソナリティに基づいて、課題が生徒にとってより身近なものとなるよう授業導入の工夫を改善・改良を進めることができた。, In order to promote collaborative learning, we have made it possible to display and compare the results of observations and ideas based on that on a tablet terminal. As a result, they promoted the formation of new ideas. In addition, the average value of awareness that "I want to convey my thoughts to other people" and "I notice that I did not notice myself when I talked with other people" increased, and significant differences were recognized. In the teacher training by Blended Learning, I showed the teaching plan of the example class example and the situation of the class in the image and proceeded the class research. As a result, based on the actual conditions of each school and the personality of the teaching teacher, it was possible to improve and improve the device for introducing classes so that the task became closer to students., 15H02919
- 知識・技能を活用する力を育成するための授業改善の阻害要因・促進要因の研究, Study on factors that impede improvement of lesson and promoting factors to foster the ability to utilize knowledge and skills, 藤本 義博; 荒尾 真一; 益田 裕充; 野稲 幸男; 鈴木 康浩; 石黒 奈央; 波平 長真; 神 孝幸; 奈良岡 奈央; 小倉 恭彦; 三浦 真一; 吉武 美岐, FUJIMOTO YOSHIHIRO; ARAO Shinichi; MASUDA Hiromitsu; NOINE Yukio; SUZUKI Yasuhiro; ISHIGURO Nao; NAMIHIRA Nagamasa; JIN Takayuki; NARAOKA Nao; OGURA Yasuhiko; MIURA Shinichi; YOSHITAKE Miki, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究, Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 挑戦的萌芽研究, Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 国立教育政策研究所, National Institute for Educational Policy Research, 2016年04月01日, 2018年03月31日, 主体的・対話的で深い学びの授業を実践した教師は,「周囲と対話し,検証,考察することに楽しさや重要性を見いだしている生徒がいたことから,このような授業を実践することで,資質・能力の育成に繋がると考える。」「今回はモデル実験を通して理解が深まったと答える生徒が多かったので,これから積極的に授業に取り入れていきたいと思った。」など,主体的・対話的で深い学びを実現した授業を行い生徒の反応を体験することは促進要因であるといえる。「モデル実験にしろ,授業者が1人でアイディアを出し実践することは大変難しい」と回答していたことから,授業研究に協働で取り組むため理科教員同士の繋がりを構築することが大切である。, A teacher who practiced interactive, deep learning lesson said, "Since there were students who have found pleasure and importance in dialogue, verifying and considering surroundings, practicing such classes I think that it will lead to the development of qualities and abilities. "," Many students answered that their understanding was deepened through model experiments this time, so I wanted to positively adopt them into the class from now on. " It can be said that promoting students' reactions by conducting lessons that realize interactive and deep learning is a driving factor. "It is very difficult for class teachers to put out ideas and practice by themselves, either model experiments." It is important to build a connection between science teachers so that they can collaborate on lesson research is there., 16K12775
- 科学的リテラシーを育成する天文分野の探究学習プログラム開発に関する実証的研究, Empirical studies on development of inquisitive learning program in the field of astronomu to promote science literacy, 栗原 淳一; 小林 辰至; 濤崎 智佳; 益田 裕充, Kurihara Jun-ichi, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 群馬大学, Gunma University, 2015年04月01日, 2018年03月31日, 本研究では、空間認識能力が必要とされる中学校天文分野の学習を対象に、科学的リテラシーを育成する学習プログラムを開発し、その指導の効果を実証的に明らかにした。 特に満ち欠けの学習では、天体の位置関係を位相角でとらえさせ、モデル実験用教材で満ち欠けと位相角の関係についての仮説を検証させる指導が有効であることが明らかとなった。現象とそれを引き起こす要因との因果関係について仮説を設定させ、それを検証させる探究的な学習に作図を導入することは、現象を科学的に説明する能力の育成に有効であることが示唆された。, In this research, we developed a learning program to foster scientific literacy for learning in lower secondary school astronomy field which is in need of spatial recognition ability, and empirically clarified the effect of guidance.Especially in moon and venus phase learning, it was clarified that teaching which verify the hypothesis about the relation between the positional relation of celestial bodies and the phase angle by model experiment is effective.It was suggested that introducing drawing activities on learning to verify the hypothesis is effective for nurturing the ability to explain phenomena scientifically., 15K04407
- 理科授業を通して学び続ける教師教育プログラムの開発に関する実証的研究, Empirical research on development of educational program for teachers who keep learning about effective teaching methods in science lesson, 益田 裕充; 鈴木 康浩; 藤本 義博; 片平 克弘; 森本 信也; 久保田 善彦, MASUDA HIROMITSU, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 基盤研究(B), Grant-in-Aid for Scientific Research (B), 群馬大学, Gunma University, 2013年04月01日, 2017年03月31日, 本研究はPLCとDBSの理論に基づいて、教師の資質・能力形成のプロセスを明らかにし、理科授業を通して学び続ける新たな教師教育プログラムを開発することである。研究の成果として、理科授業の「問題解決の過程」をコアにした授業カンファレンス、リフレクションのプログラムが、「集団としての一般化」、「課題解決の連動性・適応性」を高めることが明らかとなった。, The purpose of this research is to develop educational program for teachers who keep learning about effective teaching methods in science lesson by analyzing the process to cultivate their ability on the basis of theory of “PLC” and “DBS”. The research clarifies that science lesson including methods of conference and reflection with an emphasis on the process of program solving generalize students’ understanding in class and improve the way to take advantage of program solving skills., 25282032
- 子どもの科学的リテラシーを育成する教育システムの開発に関する実証的研究, Positive Research on Development of Educational System for Children's Studying Independently and Liking Science, 五島 政一; 小林 辰至; 熊野 善介; 下野 洋; 益田 裕充; 平田 大二; 岡本 弥彦; 小川 義和; 境 智洋; 田代 直幸; 清原 清一; 日置 光久, MASAKAZU Goto, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(A), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (A), 基盤研究(A), Grant-in-Aid for Scientific Research (A), 国立教育政策研究所, National Institute for Educational Policy Research, 2011年04月01日, 2015年03月31日, 各研究機関は,それぞれ主体的に研究活動を推進し,W型問題解決モデルに基づいて,子どもの科学的リテラシーを育成するカリキュラムを開発し,指導できる教師を育成する長期と短期の教師教育プログラムを開発・実践することを通して教育システムの開発を行う。相互に緊密な連携を取り,横断的・総合的に研究を進め,教師教育プログラムの体系化を図る。, Each study oraganization promotes autonomous study organizations ,and develops curricula for children’s scientific literacy on the basis of the W-style problem-solving model. It develops educational systems thorough developing and practicing in-service educational programs for the long-term and short-term period. It promotes mutual coopration and promotes their research mutually and organically and organizes systematizing in-service teacher’s educations. Or practical examples for the teacher’s making the typical practices for the fostering of children scientific literacy should be positive studied for it., 23240107
- IRF発話連鎖構造分析を言語活動の評価に用いた教師の授業力形成に関する実証的研究, Research on improvement of the ability to evaluate language activities by IRF analysis, 益田 裕充, MASUDA Hiromitsu, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究, Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 挑戦的萌芽研究, Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, 群馬大学, Gunma University, 2012年04月01日, 2014年03月31日, 我が国の授業において言語活動の充実が求められている。しかし、多くの教師は言語活動の充実を質的に評価できない現状にある。そこで、本研究は初任者と熟達者がIRF三項発話連鎖構造分析の手法を用い、言語活動を質的に評価する能力を向上させながら、授業力形成のいかなる知見を省察できるのか実証した。特に、熟達者が連鎖機能を高め対話の質を向上させていく過程を省察できた。, The improvement of language activities in class is required in Japan. However, teachers cannot evaluate the quality of them sufficiently. Research demonstrates reflection in order to improve language activities with enhancing ability to evaluate them by the analysis of IRF sequence that mature and immature teachers evaluate contents each other. Consequently, teachers could reflect the process that mature teachers enhance quality of dialog and sequence in the activities., 24653267
- デジタルコンテンツとモデル実験とを有機的に結び付けた天文学習プログラムの開発, 岡崎 彰; 栗原 淳一; 益田 裕充, 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 群馬大学, 2011年, 2013年, 本研究の目的は、デジタルコンテンツと理科室のモデル実験とを有機的に結び付けた教材を開発し、新たな視点から展開する天文学習指導プログラムを提案することである。当初の研究実施計画では、(1)「月の満ち欠け」と(2)「日食と月食」で教材開発とそれに基づく天文学習指導プログラムの開発、(3)「太陽の年周運動」と(4)「惑星の動き」で実際に観測された動画や画像を用いた教材開発をテーマに取り組むこととした。 (1)「月の満ち欠け」では、月と太陽の離角を媒介として実際の観察結果とモデル実験とを有機的に結び付ける教材と学習プログラムを開発し、公立中学校で授業実践を行った。生徒の理解度の調査・分析の結果、開発した授業が学習内容の理解を促し、その定着を図る上で有効であり、観察記録とモデル実験結果の関連付けを図る上でも有効であることを明らかにした。 (2)「日食と月食」では、予備的に開発した教材を用いて公立中学校でモデル実験の授業実践を行い、また、平成24年5月の金環日食では大学内で事前説明会と観察会を実施した。教材の改良と学習プログラムは期間内に完成していないが、本物の日食や月食とモデル教材との結びつきを生徒に実感させることの重要性やモデル教材の作成上の留意点等を考察した。 (3)「太陽の年周運動」と(4)「惑星の動き」については、研究期間の短縮もあり次のように統合した形で進めた。恒星に対する太陽や惑星の動きを直接に観察できる素材として太陽観測衛星が太陽と惑星と恒星を同一視野に撮影した実写動画(NASAが公開)に着目し、中学校授業「太陽の年周運動」での利用の有効性を実践例に基づいて論じ、さらに高校地学の探究活動として、この動画を教材とする「合」付近での「惑星の動き」の具体例を提案した。 このほか、関連研究として、天球の内側からと外側からとの視点移動を支援する実験用モデル教材作成についても考察した。, 23531240
- 教えて考えさせる理科授業の創造-演繹的推論に基づく習得型理科授業の構築-, Lesson Study of the Science which United Teaching and Making it Think : Construction of Lesson Study of Science Based on Deductive Reasoning, 益田 裕充; 岡崎 彰; 佐々木 剛, MASUDA Hiromitsu; OKAZAKI Akira; SASAKI Tuyoshi, 日本学術振興会, Japan Society for the Promotion of Science, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 基盤研究(C), Grant-in-Aid for Scientific Research (C), 群馬大学, Gunma University, 2009年, 2011年, 本研究は、理科授業における推論の過程を検証した。理科学習指導案の収集・分析によって演繹的な方略が授業で用いられている実態を調査した。そこで、授業は教科書で用いられている推論に依存して構築される事例を抽出できた。次に、演繹的な方略による理科授業を中学校で1、小学校で5つ実践し調査した。小学校の授業で演繹的な方略が学習者の科学的概念の獲得に影響する事例を抽出できた。さらに、一般法則を実験で証明させる演繹的な方略の提案とその有効性、学習者の予想の局面における学びの深化、情意面の変容を実証できた。, This study aims to test a process of speculation during the science classes and investigate the actual conditions where deductive approach is adopted by means of gathering and analyzing of teaching plans for science class. The case where the class was structured based on the speculations on textbooks was found. Then the science classes which adopted deductive approach were conducted and observed in a class at junior high school and five classes at elementary school. The case where the deductive approach affected learners' obtainments of scientific concepts was discovered at elementary school. In addition the deductive approach which experimentally demonstrates the general law is suggested. Moreover its effectiveness as well as the learners' deep understandings and emotional changes in speculating are verified., 21530915
社会貢献活動情報
社会貢献活動
- 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編 学習指導要領等の改善に係る検討に必要な専門的作業等協力者(中学校理科), 2015年, 2017年(対象:教育関係者, 研究者, 学術団体)
- 全国学力・学習状況調査問題作成・分析委員会委員 副主査, 2015年, 2016年(対象:教育関係者)
- 国際数学・理科教育動向調査(TIMSS2015)国内専門委員(理科), 2015年, 2017年(対象:教育関係者)
- 群馬県教育委員会 教育委員, 2018年, 9999年(対象:教育関係者, 行政機関)
- 群馬県教育委員会 教育委員会の事務執行に関する第三者評価委員(座長), 2018年, 2018年(対象:教育関係者)
- 群馬県いじめ問題対策連絡協議会 委員, 2017年, 2017年(対象:教育関係者)
- 群馬県教育委員会 「確かな学力」の育成プロジェクト会議 委員長, 2017年, 2019年(対象:教育関係者)
- スーパーサイエンスハイスクール(群馬県立高崎高等学校)運営指導委員会 委員長, 2016年, 9999年(対象:教育関係者)
- 前橋市教育委員会 総合教育プラザ運営委員会 委員長(対象:教育関係者, 行政機関)
- 埼玉県市町村指導主事会研修会, 埼玉県教育委員会, 2012年12月
- 神奈川県教育委員会第1回指導方法改善研修講座, 2014年07月
- スーパーサイエンススクール(群馬県立高崎高等学校)運営指導委員長, 群馬県教育委員会, 2015年, 9999年
- 理科の観察・実験指導等に関する研究協議会, 群馬県教育委員会, 2015年12月
- 全国中学校理科研究発表会指導者, 2016年08月
- 初任者研修に関わるメンターの活用について, 群馬県総合教育センター, 2016年10月
- 新しい学習指導要領を踏まえた確かな学力の育成とは, 皆野町教育委員会・埼玉県教育委員会, 2016年11月
- 群馬県総合教育センター初任者研修に関わるメンターの活用について, 群馬県総合教育センター, 2017年07月
- 群馬県総合教育センター15年次研修, 群馬県教育委員会, 2017年05月
